広義には「コンピュータ音楽」の領域に含まれる、メディア・アート、
インタラクティブ・アート、メディア・インスタレーション等に
ついて、その特性と関係について考察するとともに、静岡文化芸術大学
における学生の具体的な作品制作・発表の過程を分析的に調査すること
により、新しい表現と芸術創造の可能性について検討した。
1. はじめに
「コンピュータ音楽」は下図のように、狭義には音楽情報処理システムとしてある程度閉じた世界を構成しているが、コンピュータシステムと人間・外界とのインターフェースとしてセンサ技術を取り入れた広義のコンピュータ音楽の世界では、所謂メディア・アート、インタラクティブ・アート、メディア・インスタレーション等もその一つの形態として認知されるようになった[1][2]。
2000年4月に開学した静岡文化芸術大学(SUAC)デザイン学部技術造形学科では、多くの領域でのデザインの一つとして、この広義のコンピュータ音楽をテーマとした作品制作活動を既に開始してきた[3]。本稿では、この広義のコンピュータ音楽の特性について考察するとともに、SUACにおける具体的な作品制作・発表の過程を分析して、新しい表現と芸術創造の可能性について検討した。
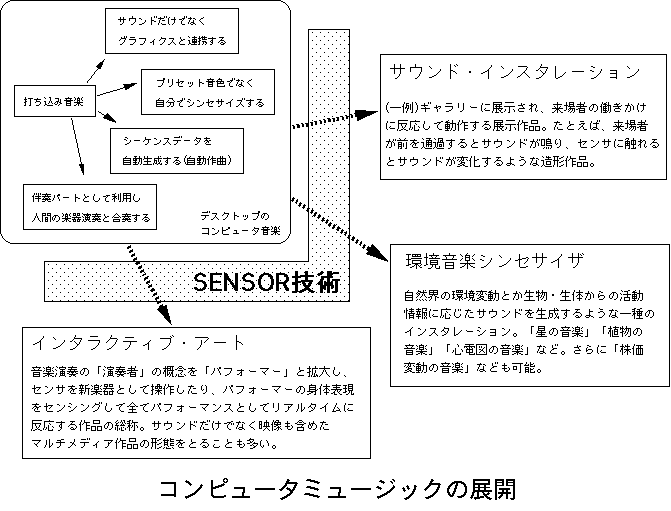
2. インスタレーション
2000年5月28日に開催された「SUAC一般公開デー」において、教員と有志学生によつて共同制作した作品 "森海" は、センサを活用した典型的なメディア・インスタレーションであった[3]。ここでは大型プラズマディスプレイを8台並べたスペース内で、来場者の移動を赤外線ビームセンサでセンシングして、Maxにより画像とサウンドとをインタラクティブに駆動した。このような作品は、一種のギャラリーである展示空間に次々と来場者が訪れるような場で有効であるが、あまり混雑していると誰の動きにシステムが反応しているかが判らなくなる、という課題も発見できた。サウンドの部分を聞かせたい、という意図が強い場合にはこの課題はかなり重大な問題となりうる。
3. パフォーマンス
2000年9月17日「インタラクティブ・メディアアート」というタイトルのシンポジウムの場で公演した作品 "Wandering Highlander" は、古典的な意味でのパフォーマンスを伴ったインタラクティブ・メディアアート作品であった[3]。
ここでは、両手首・両肘・両肩の関節の曲げセンサを装着したPerformerのダンスにより、固定的再生でなくリアルタイムに音楽と映像が生成・駆動された。Maxによりセンサ情報を音楽・グラフィクスのシステムとリアルタイムに結び付ける、という意味では前述のインスタレーションと同じであるが、ステージ様のスペースで「開始」と「終了」という概念を自然に提供することで、間違いなく、これはパフォーマンス(演奏)であった。
4. Team風虎の作品"Windmill"
2000年12月16-17日の情報処理学会音楽情報科学研究会・インターカレッジコンピュータ音楽コンサートにおいて、SUACからは初めて、学生だけで制作した作品を対外発表した[3]。形態としては、「造形作品を用いたパフォーマンス」という作品のライブ公演である。これは図Aの広義のコンピュータ音楽の形態において、ある意味ではインスタレーション、ある意味では自然の状況を受け(光に反応)、そして「演奏時間」を持つパフォーマンス作品、でもあるという欲張ったものである。

この作品 "Windmill" は上図のように、ステージ上に大小4個のオリジナル造形作品(光を受けて回る「風車」)があり、ここにライブ制御の照明や、サーチライトや光の遮蔽物を持ったperformersが加わったパフォーマンスを行うものである。風車は変化する光とともに動きが変化し、この変化をセンシングした情報がMax上のアルゴリズム作曲系を駆動して、背景音響系とともに全体のサウンドを構成した。
5. 自己評価と考察
この作品は、ステージ上に設置されたオブジェだけを見ていると、そのままインスタレーション作品としてロビー展示をしても通用する、と見えたかもしれない。しかし共同でこの作品を制作し、演出やリハーサルを重ねてPerformanceに至ったプロジェクトメンバーのレポート等を検討すると、間違いなくこの作品はインタラクティブ・パフォーマンス作品であったことが判る[4]。
インスタレーション作品は来場者にその鑑賞の形態・方法・姿勢・時間などを自由に委ねるのに対して、パフォーマンス(公演)の形態をとる作品は、客席で静かに鑑賞すること、そして上演時間という制約を聴衆に強制することになる。その一方で、インスタレーションでしばしば起きる「意図に気付かずに通過される」という問題点に対して、「演出」という要素によって積極的にメッセージや関係性をアピールすることができる。この両者はある部分では二律背反であり、メディアアート作家の永遠の課題でもあった[5]。
今回の作品 "Windmill" においては、「楽器」の延長としてのセンサという形態でなく、明らかにオブジェ、という造形作品としての要素を強く打ち出すとともに、背景音楽やPerformerに対応するサウンドの部分では音楽作品であった。そして人間とセンサとの間に「光」という自然環境要因が介在するとともに、複数のPerformerが振り付けまで考慮してパフォーマンスすることで、そこに独特な表現空間を実現できた。筆者のこれまでの作品ではセンサは「広義の楽器」の範疇を超えるものではなかったが、期せずして到達したこの新しい可能性は新鮮なものであった。もちろん、今回の公演を見て「自分で光を操って風車を回したり鳴らしてみたい」という感想を持った聴衆もおり、これはこの作品がインスタレーションへと進化する可能性も示している[5]。
6. おわりに
今回の作品によって、メディアアートの新しい可能性をあらためて知ることができた。今後も机上の空論でなく、実際の作品制作やシステム構築の具体的な進展とともに研究を進めていきたい。
参考文献
[1] 長嶋洋一「コンピュータサウンドの世界」、CQ出版、1999年
[2] 長嶋・橋本・平賀・平田編「コンピュータと音楽の世界」、共立出版、1998年
[3] 長嶋洋一「静岡文化芸術大学スタジオレポート」、
情報処理学会研究報告 Vol.2000,No.118 (2000-MUS-38)、情報処理学会、2000年
[4] http://nagasm.org/
[5] http://nagasm.org/1106/
|