音楽理論特訓集中講座 (長嶋)
メニュー(案)
- 音の3要素、音楽の3要素
- 楽典(1) 音の高さ
- 楽典(2) 音の長さ
- 楽典(3) 鍵盤と全音階 diatonic scale
- 楽典(4) 楽譜と記号
- 楽典(5) 音程 interval
- 楽典(6) キー、調号、調性、五度円 cycle of fifth
- 楽典(7) 3和音、自然倍音、協和感
- 楽典(8) 4和音から面白くなる
- 楽典(9) 和音の種類とコードネーム
- 楽典(10) 分数コード
- ギターとベースの音楽的構造について
- ドラムセットとパーカッション
- バンドスコアの読み方 : タブ譜とドラム譜
- 総譜の読み方 : 移調楽器とハ音記号
- まずはとりあえず打込みしてみよう
- MIDIの話
- DTMソフトウェアと音源ドライバ
- 打込み前の準備(キー、拍子、音部記号、チャンネル、音色)
- メロディーを入れる
- コピーペーストと繰返し記号
- デュレーション duration と表現
- テンポと表現
- いよいよアレンジに挑戦しよう
- メロディーを際立てる
- バッキングコードを入れる
- ベースを入れる
- ドラムを入れる
- リズム/ビートの代表的なパターン
- ボリューム、パンポット、エクスプレッション
- ピッチベンドのテク
- バランス(音量/音色/時間差)によるアレンジ
- 楽典(11) コード進行とコードの機能(T/SD/D)
- 楽典(12) ドミナントモーションと終止感
- 楽典(13) トライトーンと終止感
- 楽典(14) ベースの進行(P4/P5/semitone)と重力
- 楽典(15) NDC、代理コード、裏コード、「音を抜く」
- 楽典(16) カデンツァ、ブルース、循環コード、II-V
- 楽典(17) スケール(Diatonic/Pentatonic/Chromatic/WholeTone/Minor4種)
- 楽典(18) ダイアトニックコードのテンション available note scale
- 楽典(19) USTと教会モードスケール
- 楽典(20) マイナースケールとSec.Dのコードスケールのテンション
- オリジナルのアレンジへ
- ヘンな音/効果音の作り方
- ギターっぽい奏法、ピアノっぽい奏法、ベースっぽい奏法
- ドラムのフィルイン(オカズ)とパーカッション
- 裏メロとハモり(ボイシング)
- コードのリハーモナイズ
- 転調と「調性の進行」
- プロの技に学ぶコツ
- 定番スタイル(1) 8ビートのロック
- 定番スタイル(2) 16ビート
- 定番スタイル(3) 4ビートのジャズ
- 定番スタイル(4) シャッフルとバラード
- 定番スタイル(5) ラテン
- 定番スタイル(6) レゲエ
- 定番スタイル(7) テクノ/ユーロビート
- 定番スタイル(8) 演歌
- 定番スタイル(9) フュージョンと変拍子
- 定番スタイル(10) ウインナワルツと3拍子ロック
- サンプリングサウンドの活用
- エフェクトの活用
- 音律 temperaments
- 「耳コピー」のやり方
- バンマスへの道はアレンジの道
- アレンジから作曲へ
特講テキスト
以下のテキストは1文字もコピペせず、全文を長嶋洋一が書き下ろして執筆したテキストです。 このページをリンクで紹介するのはOKですが、無断で「自分の文章」のごとくコピペする事はお止め下さい。(_o_)楽典とは
楽典とは音楽を記述する上での共通ルールなど。音楽を理解したかったらこれは必須。音の3要素、音楽の3要素
音の3要素「高さ」「強さ」「音色」のうちここでは高さ(ピッチ)が当面の注目点。 音楽の3要素「メロディー」「リズム」「ハーモニー」は全て扱うが、当面コードを理解するには ハーモニーの部分に注目。講座(1) 音の高さ
「音高」を「音程」と間違えないこと。音程とは2つの音の相対的なへただりintervalのこと。 ピッチは毎秒の振動数で決まり、サウンドは2倍の振動数(オクターブ)になると同じピッチの性質(pitch class)に回帰する。 よって音の種類はオクターブの中だけで考えて、これを越えたら適当にオクターブ上下させる。 12等分平均律では、1オクターブを等間隔の周波数(振動数)比に分割するので、基本単位となる「半音」の振動数比は 「12乗根の2」、つまりこれを12回掛けると2になる数(1.058...)。 半音が2つ分の音程は「全音」。 この講習ではアメリカ式にとりあえず読む。ハニホもツェーデーエーも無し。講座(2) 音の長さ
音の長さdurationは、減衰する音の場合曖昧となる。今回の講習では楽典にある 音符・休符の部分は自分で確認しておくこと。講座(3) 鍵盤と全音階 diatonic scale
鍵盤というのは等間隔でないヘンな並びの道具、しかしこれが実は人類の感性の基礎である。 ピアノを習って「固定ド」だけの人は、和声の理屈を体感できない不幸な人。 12種類の全ての音が「ド」となりうる、というところから音楽は始まる。 一般の音楽鍵盤では、Cをド、あと白鍵を順にDレ、Eミ、Fファ、Gソ、Aラ、Bシ、とする。 12個のうちここで登場する音が7個である、というのが最大のポイント。 間にある5個の音は、両側の音からシャープで上げたりフラットで下げたりして名付ける。 Cの半音上の音はC#、あるいはDb、この2音は同じである。 オクターブから7個の音を選ぶこのルールは、スタートの基準であるrootのドから、順に上に、 全音レ、全音ミ、半音ファ、全音ソ、全音ラ、全音シ、半音ド、となっている。 この7つの音だけを使うと、どうデタラメやってもそれなりの音楽に聞こえる。 オルゴールや岩井俊雄さんの作品の秘密はこれ。 これをダイアトニックスケールと言う。 この7音からさらに「ヨ」「ナ」を抜いた5音は、rootを移動すると5個の黒鍵と同じ 相対関係になる。これをペンタトニックスケールと言う。 この5音は「猫ふんじゃった」とか演歌とかを構成する。日本人には懐かしい。 世界の民族音楽もこれがとても多い。講座(4) 楽譜と記号
楽譜(5線譜)はとりあえずの道具。ただしこれも等間隔でないヘンな並びの道具である。 ト音記号により基準の高さを決める。 5線譜では、線と間ごとに音を並べると、オクターブに7個の音しか書けない。 これは鍵盤に対応している。 楽譜と鍵盤とそれぞれのピッチとは、ちょっと考えたらスグに相互変換できるように しておくこと。 ある小節の中で、ある音を楽譜のピッチより半音上げるシャープ、半音下げるフラットなどの 臨時記号の効力は、その小節内で有効である。次の小節に入るとリセットされる。 臨時記号を臨時に取消すのはナチュラル。講座(5) 音程 interval
2音の高さのへただりはコードを機械的に理解するために必要なので、以下の用語を覚えること。 同じ高さの音は1度。5線譜で隣の高さ(もっとも密接している)のは2度。これには、 半音1個の「短2度」(例えばE-F)と、半音2個(全音)の「長2度」(例えばD-E)がある。 5線譜で隣の線同志、あるいは隣の間同志は3度。これには、 半音3個の「短3度」(例えばE-G)と、半音4個の「長3度」(例えばF-A)がある。 5線譜で3度+2度の間隔は4度。これには、 半音5個の「完全4度」(例えばC-F)と、半音6個の「増4度」(例えばF-B)がある。 5線譜で3度+3度の間隔は5度。これには、 半音7個の「完全5度」(例えばC-G)と、半音6個の「減5度」(例えばB-F)と、半音8個の「増5度」(例えばC-G#)がある。 5線譜で5度+2度の間隔は6度。これには、 半音8個の「短6度」(例えばA-F)と、半音9個の「長6度」(例えばC-A)がある。 5線譜でオクターブ-2度の間隔は7度。これには、 半音10個の「短7度」(例えばD-C)と、半音11個の「長7度」(例えばC-B)がある。 オクターブ+2度なら9度、オクターブ+4度なら11度、など、これはまだまだある。 他にもまだ細かいのはあるが、たいていはこの中で話が出来るので省略。

講座(6) キー、調号、階名
カラオケで声域に対応して「キー」を上下しても、その音楽はまったく変わらない。 これは「移調」している、つまり基準となるrootを曲全体で平行移動して上下させている(「転調」とはまったく違うことに注意)。 そこで、白鍵盤でなく、Cでない基準からドレミ・・・(階名)を構成してみる。 ここでは例えば、「Dをド」とすることにする。すると、rootのDのドに対して、 ドレミの音階(階名)の音程は順に上に、 全音レ、全音ミ、半音ファ、全音ソ、全音ラ、全音シ、半音ド、となっているので、 具体的な音名を考えると、D-E-F#-G-A-B-C#-Dとなる。 ここで、いちいちFとCを、臨時記号を付けてF#とC#にする、というのが、 不幸な固定ドのセンスの持ち主で、それをやるとハーモニーがいつになっても 理解できない。 移調して、ドレミが登場すれば必ずFとCはF#とC#になるのであれば、 それをト音記号の横にまとめて定義してしまえばいい。 これが「調号」である。実際、D-majorという調性では、調号として FとCの位置にシャープが書かれている。これにより、そのシャープの位置だけ でなく、オクターブ上下のFとCについても、必ず、F#とC#となる。 そうすると、このような調号のある楽譜では、臨時記号は付いていないが、 一見するとFとCのような音も、楽譜の左端の調号が常に効いていて、 必ずF#とC#となる。D音をスタートrootとして、安心してドレミと読める。 これが「移動ド」である。これが出来ないと和声は体感として理解できない。講座(7) 自然倍音、協和感
人間は何故、メジャー3和音を聞くととりあえず嬉しいのか。その秘密は数学と物理、つまり宇宙の真理である。 ある音をf(Hz)とする。同一であるf自身、の次にfと協和する(違和感が無い)のはオクターブ上、つまり2fの音。 この2音はもっとも単純な1:2の整数比である。 となると次は3倍音(3f)。これはfの音の「オクターブと純正完全5度」(1:3)である。 1:3というのはオクターブを越えているので、片方をオクターブ上げると、整数比は2:3。 この2:3を「純正完全5度」と言う。平均律の完全5度は純正ではなくて非常に小さいズレがあるが、 素人には識別できないぐらいの誤差。この、平均律の完全5度がほぼ純正完全5度である、 というところから近代の和声理論が構築されている。 この完全5度、あるいはオクターブ転回した完全4度、という音程は「無色透明」である。 和音を構成する枠組みでしかない。色が付くのはこの後である。 1:3の3倍音(3f)の次は4倍音(4f)、これは単なる2オクターブなのでパス。 その次は5倍音(5f)。これはfの音の「2オクターブと純正長3度」(1:2)である。 オクターブ内にするため片方を2オクターブ上げると、整数比は4:5。 この4:5を「純正長3度」と言う。平均律の長3度は純正からのズレかなり大きく、 素人でもその違いは簡単に判る。ところが近代人は、産まれた時から平均律の濁った長3度を 聞いてきているので、むしろこちらが自然で、純正長3度の唸りの無い協和感には空虚な不安感を持つ。 ここはこれ以上深入りしないが、音楽の深淵である「純正な響き」の入り口である (興味のある人は僕の書いた 音律についてをじっくり勉強してみて)。 この次の6倍音(6f)は3倍音のオクターブなのでパス。 その次の7倍音(7f)は、無理に平均律の中で近似するとすれば「フラット気味の短7度」であるが、 あまりに誤差が大きく、平均律では単純な整数比とならないので除外する。次の8倍音は3オクターブでパス。 これ以上はとりあえず省略する。 さて、ここで出て来たオクターブ以外の2つの基本音程は、「完全5度」(2:3)と、「長3度」(4:5)。 これを3和音としてまとめるには2:3を転回して3:4(完全4度)と見れば「3:4:5」となる。 4が基準のfのオクターブなのでこれがド、つまり「3:4:5 = ソドミ」の長3和音である。 あるいはソをオクターブ上げると「4:5:6 = ドミソ」の長3和音である。 これはもっとも単純な3つの整数比である。人間がもっとも協和した3和音として聞くのは、 もっとも単純な整数比であるmajorの3和音ということになる。 そして、その次に単純な整数比はminorの3和音である。だから人類はメジャーとマイナーの 2種類の和音があればとりあえずは満足してしまう。 簡単なminorの作り方として「ラドミ」を目指す。ドミは既に出ているが、純正なラをどう作るか。 実はラは、ファの純正長3度として作れる。ではファは・・・というと、ファからドは完全5度である。 これが2:3なので、基準となるドに素因数3を必要とする。ここではドを12f、とする。 このド(12f)から完全5度下がった純正なファは8f。そこから純正長3度上がったラは、 8f * (5/4) = 10f。また、ド(12f)から純正長3度上がったミは、12f * (5/4) = 15f。 つまり、これは「ラドミ =10:12:15」の短3和音である。 ドミソの長3和音とラドミの短3和音のそれぞれのrootを同じ20に並べると、 major = 20:25:30、minor = 20:24:30、となる。 つまりmajorとminorの運命の分かれ道となる第3音の振動数は、ここでの25と24だけの違いである。 人類が文化文明地理歴史を越えて、音楽の和音に共通の感情を抱く理由は、 「簡単な整数比となる音程は協和していて気持ちいい」という原理から来ている。講座(8) 5度円 circle of fifth (cycle of fifth)
オクターブを同一とすれば、音楽でもっとも基本的な「意味を持つ音程」は完全5度である。 そして12等分平均律の完全5度は、ラッキー(宇宙の偶然)なことに純正完全5度とほぼ一致している。 そこで、完全5度(以下「p5」(perfect 5th)と書く。半音7個。この「7」が実はとても重要)だけを使って、 音楽の枠組みを全て構成していこう。 スタートラインとして何かの基準を決める。とりあえずCとする。 これは単なるCの音でも、C majorという和音でもない。音楽の全体の構造(調性)の 枠組みの基準となる音高、Tonal Center(調的中心)、という意味である。 楽譜であれば「Key = C」ということで、たまたま偶然であるが、調号にはフラットも シャープも無い、という記号である。このCをTonal Centerのrootとして考える。 以降の議論はこのTonal Centerのrootを12音のどれにしても平行移動するだけで 全て成立する。 基準のCから、とりあえずp5だけ上げるとGとなる。そこで「C-G」と連鎖がスタートする。 Gからp5上げると、オクターブ上のDとなる。オクターブは適宜、上下して1オクターブの中に 移動できるので、連鎖は「C-G-D」となる。以下同文で、p5だけ上げていくと、 「C-G-D-A-E-B」となる。Bからp5上げるとF#となり、その次はC#となり、その次はG#である。 ここらまでまとめると「C-G-D-A-E-B-F#-C#-G#」となる。 ここで最初のCに戻って、今度はp5だけ下げていく。p5だけ下げるというのは、転回した p4(完全4度、半音5個)だけ上げるのと同等である。 この連鎖を左に延ばすと、Cのp5だけ下はF、その下はBbとなる。つまり 「Bb-F-C」である。同文でさらにp5だけ下げたものを左に延ばすと 「Gb-Db-Ab-Eb-Bb-F-C」という並びとなる。 これを、最初にスタートラインとしたCを中心に連結すると、 「Gb-Db-Ab-Eb-Bb-F-C-G-D-A-E-B-F#-C#-G#」となる。 たくさん音があるが、実は、Gb=F#、Db=C#、Ab=G#、と同じ音を重複している。 そこで、同じ音のところまでで連結すると、 「Gb-Db-Ab-Eb-Bb-F-C-G-D-A-E-B-F#」 「Db-Ab-Eb-Bb-F-C-G-D-A-E-B-F#-C#」 「Ab-Eb-Bb-F-C-G-D-A-E-B-F#-C#-G#」 などとなる。いずれも両端の2音は同じ音であり、全ての構成音は12個である。 つまり、完全5度、p5だけで12の全ての音を生み出すことができる。 この12個の音を円環上に並べたものを「5度円」 circle of fifth と言う。 5度円はp5の連鎖であるが、p5とp4は裏表の関係にあるので、右回りにp5した5度円は、 左回りにp4で作った5度円そのものである。右回りにp4した5度円は、単なる裏返しなので、 これは基本的に1種類だけしかない。 この他に平均律の12個の音を生成する基本音程はあるか。 「半音」は、当然ながら12個の音を生成する。転回系の長7度(半音11個)も同様である。 これはあまりに当たり前なので除外する。 これ以外の音程の場合、実は、12音を生成できない。つまり不完全な音程である。 例えば「全音」。Cから始めると、C-D-E-F#-G#-A#-Cとなって、12音のうち半分の 6個しか生成できない。短3度は半音3個なので、C-Eb-F#-A-C、と12音のうち4音しか 生成できない。長3度は半音4個なので、C-E-G#-C、と12音のうち3音しか 生成できない。半音5個はp4、そして半音6個の増4度あるいは減5度は、C-F#-Cと、 12音のうちたった2音しか生成できない。他の音程は全て以上の転回形である。 結論として、多種の音程のうち、p5つまり完全5度だけが、平均律の12個の音宇宙を生成することが できる「素粒子」である。そしてこのp5が、オクターブ以外でもっとも協和する音程である。 近代和声理論は、この基本的な音程であるp5を中心に構成されている。 例えば、楽譜で臨時記号を添えずに登場する音はオクターブに7つしかない。 このダイアトニックスケールの7音は、5度円上では、「順に隣接する7音」である。 どのキーでもそうなることを確認すべし。 また、ペンタトニックスケール(ドレミソラ、など)の5音は、 5度円上では、「順に隣接する5音」である。どのキーでもそうなることを確認すべし。 つまり、5度円という地球儀の上での距離は、そのまま音楽的な仲の良さ、 音楽的な親戚関係、などに対応する。講座(9) 調性と5度円
「完全5度(p5)」と「5度円」という道具により、12等分平均律の体系をさらに整理する。 まず、5度円と調性について。とりあえずのスタートをCとする。 ここでのCは、音高としてのCでなく、C majorというメジャーコードをrootとする枠組み、 「調性としてのC」(ハ長調)である。 「調性としてのC major」は、rootのCをドすると、ダイアトニックスケールのドレミファソラシドは C-D-E-F-G-A-B-Cとなって、調号(楽譜のト音記号の横)に何も付かない。 次に、5度円でCの右隣のGに対して、「調性としてのG」(ト長調)を考える。 「調性としてのG major」は、rootのGをドすると、ダイアトニックスケールのドレミファソラシドは G-A-B-C-D-E-F#-Gとなって、必ずFがF#となるので、調号はFの位置に「シャープ1つ」となる。 次に、5度円でCの2つ右隣のDに対して、「調性としてのD」(ニ長調)を考える。 「調性としてのD major」は、rootのDをドすると、ダイアトニックスケールのドレミファソラシドは D-E-F#-G-A-B-C#-Dとなって、必ずFがF#、CがC#となるので、調号はFとCの位置に「シャープ2つ」となる。 次に、5度円でCの3つ右隣のAに対して、「調性としてのA」(イ長調)を考える。 「調性としてのA major」は、rootのAをドすると、ダイアトニックスケールのドレミファソラシドは A-B-C#-D-E-F#-G#-Aとなって、必ずFがF#、CがC#、GがG#となるので、調号はFとCとGの位置に「シャープ3つ」となる。 次に、5度円でCの4つ右隣のEに対して、「調性としてのE」(ホ長調)を考える。 「調性としてのE major」は、rootのEをドすると、ダイアトニックスケールのドレミファソラシドは E-F#-G#-A-B-C#-D#-Eとなって、必ずFがF#、CがC#、GがG#、DがD#となるので、 調号はFとCとGとDの位置に「シャープ4つ」となる。 次に、5度円でCの5つ右隣のBに対して、「調性としてのB」(ロ長調)を考える。 「調性としてのB major」は、rootのBをドすると、ダイアトニックスケールのドレミファソラシドは B-C#-D#-E-F#-G#-A#-Bとなって、必ずFがF#、CがC#、GがG#、DがD#、AがA#となるので、 調号はFとCとGとDのAの位置に「シャープ5つ」となる。 次に、5度円でCの反対側のF#に対して、「調性としてのF#」(嬰ヘ長調)を考える。 「調性としてのF# major」は、rootのF#をドすると、ダイアトニックスケールのドレミファソラシドは F#-G#-A#-B-C#-D#-E#-F#となって、必ずFがF#、CがC#、GがG#、DがD#、AがA#、EがE#(F)となるので、 調号はFとCとGとDのAとEの位置に「シャープ6つ」となる。 同様にシャープ7つの「調性としてのC#」(嬰ハ長調)があるが、ここでは省略する。 これらシャープ系の調号の場合、「いちばん右端のシャープがシ」となるので、その1つ上をドと読める。 今度は、5度円でCの左隣のFに対して、「調性としてのF」(ヘ長調)を考える。 「調性としてのF major」は、rootのFをドすると、ダイアトニックスケールのドレミファソラシドは F-G-A-Bb-C-D-E-Fとなって、必ずBがBbとなるので、調号はBの位置に「フラット1つ」となる。 次に、5度円でCの2つ左隣のBbに対して、「調性としてのBb」(変ロ長調)を考える。 「調性としてのBb major」は、rootのBbをドすると、ダイアトニックスケールのドレミファソラシドは Bb-C-D-Eb-F-G-A-Bbとなって、必ずBがBb、EがEbとなるので、調号はBとEの位置に「フラット2つ」となる。 次に、5度円でCの3つ左隣のEbに対して、「調性としてのEb」(変ホ長調)を考える。 「調性としてのEb major」は、rootのEbをドすると、ダイアトニックスケールのドレミファソラシドは Eb-F-G-Ab-Bb-C-D-Ebとなって、必ずBがBb、EがEb、AがAbとなるので、調号はBとEとAの位置に「フラット3つ」となる。 次に、5度円でCの4つ左隣のAbに対して、「調性としてのAb」(変イ長調)を考える。 「調性としてのAb major」は、rootのAbをドすると、ダイアトニックスケールのドレミファソラシドは Ab-Bb-C-Db-Eb-F-G-Abとなって、必ずBがBb、EがEb、AがAb、DがDbとなるので、調号はBとEとAとDの位置に「フラット4つ」となる。 次に、5度円でCの5つ左隣のDbに対して、「調性としてのDb」(変ニ長調)を考える。 「調性としてのDb major」は、rootのDbをドすると、ダイアトニックスケールのドレミファソラシドは Db-Eb-F-Gb-Ab-Bb-C-Dbとなって、必ずBがBb、EがEb、AがAb、DがDb、GがGbとなるので、調号はBとEとAとDとGの位置に「フラット5つ」となる。 同様にフラット6つの「調性としてのGb」(変ト長調)、フラット7つの「調性としてのCb」(変ハ長調)があるが、ここでは省略する。 これらフラット系の調号の場合、「いちばん右端のフラットがファ」あるいは「右から2番目のフラットがド」と読める。講座(10) 音程の転回
ある和音は、個々の構成音にオクターブ上下を自由に施しても、コード理論において音楽的な意味は同一である。 そこで、C-E-Gの和音(C major)の再低音のCをオクターブ上げてE-G-Cにしても、 さらにG-C-Eにしても、全てコードネームは「C」である。 これを和音の転回と言う。とりあえずは和音の転回は好きにやっても全て同じである。 変わるのは響きの部分(ボイシング)だが、まだまだ省略。 また、オクターブは半音12個なので、オクターブ内をある音程に分割すると、 残りの音程も決まる。例えば、C-Fで完全4度(5半音)、すると残りのF-Cは完全5度(7半音)である。 合計でオクターブとなる音程の組み合わせは、例えば以下のようになる。 オクターブ = 短2度 + 長7度 = 長2度 + 短7度 = 短3度 + 長6度 = 長3度 + 短6度 = 完全4度 + 完全5度 = 増4度 + 減5度・・・。 言い換えれば、「完全4度、上がる」のと「完全5度、下がる」のとは、行き先の音がオクターブで同一なので、 音楽的には同じ機能である、という事になる。これは重要。講座(11) 3和音とコードネーム
とりあえず3和音の定義。3和音とは、rootを1度(第1音/根音/基音)、rootから上3度に第3音、 rootから上5度に第5音の、3つの音から構成される和音。それぞれの和音は、 個々の構成音にオクターブ上下を自由に施しても、コードネームも音楽的機能も全て同一である。 変わるのは響きの部分(ボイシング)だが、ここでは省略。 コードネームの記号部分はrootの音名。 majorコードは特にmajorと書かない。rootから第3音までの音程は長3度(半音4つ)。 rootから第5音までの音程は完全5度(半音7つ)。「A」の構成音は、A-C#-Eである。 minorコードはrootの音名にmを添える。rootから第3音までの音程は短3度(半音3つ)。 rootから第5音までの音程は完全5度(半音7つ)。「Gm」の構成音は、G-Bb-Dである。 diminish(減和音)コードはrootの音名にdimを添える。rootから第3音までの音程は短3度(半音3つ)。 rootから第5音までの音程は減5度(半音6つ)。「Fdim」の構成音は、F-Ab-Bである。 augment(増和音)コードはrootの音名にaugを添える。rootから第3音までの音程は長3度(半音4つ)。 rootから第5音までの音程は増5度(半音8つ)。「Caug」の構成音は、C-E-G#である。 sus4(サスフォー)コードはrootの音名にsus4を添える。rootから第3音(実際は特例で4度)までの音程は完全4度(半音5つ)。 rootから第5音までの音程は完全5度(半音7つ)。「Gsus4」の構成音は、G-C-Dである。講座(12) 4和音とコードネーム
3和音はクラシックの道具。ジャズやポップスは、4和音から面白くなる (本稿では対比として「クラシック」という言葉が頻出するが、これは19世紀的/古典的/教科書的/教義的、という程度の意味)。 とりあえず4和音の定義。4和音とは、rootを1度(第1音/根音/基音)、rootから3度に第3音、 rootから5度に第5音、rootから7度に第7音、の、4つの音から構成される和音。それぞれの和音は、 個々の構成音にオクターブ上下を自由に施しても、コードネームは全て同一である。 コードネームの記号部分はrootの音名。 4和音では、一部の例外を除いて、下3和音は既に述べた3和音、ここにrootから色々な音程の7度の音が加わって構成されている。 「major 7th」コードの下3和音はmajorコードなのでrootから第3音までの音程は長3度(半音4つ)、 rootから第5音までの音程は完全5度(半音7つ)である。 ここにrootから長7度(半音11個)の7th(メジャー7thと言う)が加わる。 たとえば「Dmaj7」「DM7」の構成音は、D-F#-A-C#である。 「minor major 7th」コードの下3和音はminorコードなのでrootから第3音までの音程は短3度(半音3つ)、 rootから第5音までの音程は完全5度(半音7つ)である。 ここにrootから長7度(半音11個)の7th(メジャー7th)が加わる。 たとえば「Dm maj7」「D-M7」の構成音は、D-F-A-C#である。 「6th」コードの下3和音はmajorコードなのでrootから第3音までの音程は長3度(半音4つ)、 rootから第5音までの音程は完全5度(半音7つ)である。 ここにrootから長6度(半音9個)の6thが加わる。 たとえば「D6」の構成音は、D-F#-A-Bである。 「minor 6th」コードの下3和音はminorコードなのでrootから第3音までの音程は短3度(半音3つ)、 rootから第5音までの音程は完全5度(半音7つ)である。 ここにrootから長6度(半音9個)の6thが加わる。 たとえば「Dm6」の構成音は、D-F-A-Bである。 「7th」(ドミナント7th)コードの下3和音はmajorコードなのでrootから第3音までの音程は長3度(半音4つ)、 rootから第5音までの音程は完全5度(半音7つ)である。 ここにrootから短7度(半音10個)の7th(ドミナント7thと言う)が加わる。 たとえば「D7」の構成音は、D-F#-A-Cである。 「minor 7th」コードの下3和音はminorコードなのでrootから第3音までの音程は短3度(半音3つ)、 rootから第5音までの音程は完全5度(半音7つ)である。 ここにrootから短7度(半音10個)の7th(ドミナント7th)が加わる。 たとえば「Dm7」の構成音は、D-F-A-Cである。 このコードは第3音をrootと見ると6thコードでもある。構成音としては、「C6=Am7」である。 どちらでも間違いではない。 「minor 7th フラット 5th」コードの下3和音はdiminishコードなのでrootから第3音までの音程は短3度(半音3つ)、 rootから第5音までの音程は減5度(半音6つ)である。 ここにrootから短7度(半音10個)の7th(ドミナント7th)が加わる。 たとえば「Dm7-5」「Dm7b5」の構成音は、D-F-Ab-Cである。これは実は、 Cm-Ebの調のダイアトニックスケールで、シの上に4和音を構成したシレファラの和音である。 このコードは第3音をrootと見るとminor 6thコードでもある。「Bm7-5=Dm6」である。 どちらでも間違いではない。 「diminish 7th」コードの下3和音はdiminishコードなのでrootから第3音までの音程は短3度(半音3つ)、 rootから第5音までの音程は減5度(半音6つ)である。 ここにrootから減7度(半音9個)の6thが加わる。 たとえば「Ddim7」の構成音は、D-F-Ab-Bである。この4つの音は全て、互いに短3度(半音3つ)なので、 どれをrootとしても同じとなる。Ddim=Fdim=Abdim=Bdimである。 「augment 7th」コードの下3和音はaugmentコードなのでrootから第3音までの音程は長3度(半音4つ)、 rootから第5音までの音程は増5度(半音8つ)である。 ここにrootから短7度(半音10個)の7th(ドミナント7th)が加わる。 たとえば「Daug7」の構成音は、D-F#-A#-Cである。 「ドミナント7th フラット 5th」コードのrootから第3音までの音程は長3度(半音4つ)、 rootから第5音までの音程は減5度(半音6つ)である。 ここにrootから短7度(半音10個)の7th(ドミナント7th)が加わる。 たとえば「D7-5」「D7b5」の構成音は、D-F#-Ab-Cである。 「7th sus4」コードの下3和音はsus4コードなのでrootから第3音までの音程は完全4度(半音5つ)。 rootから第5音までの音程は完全5度(半音7つ)である。 ここにrootから短7度(半音10個)の7th(ドミナント7th)が加わる。 たとえば「D7sus4」の構成音は、D-G-A-Cである。
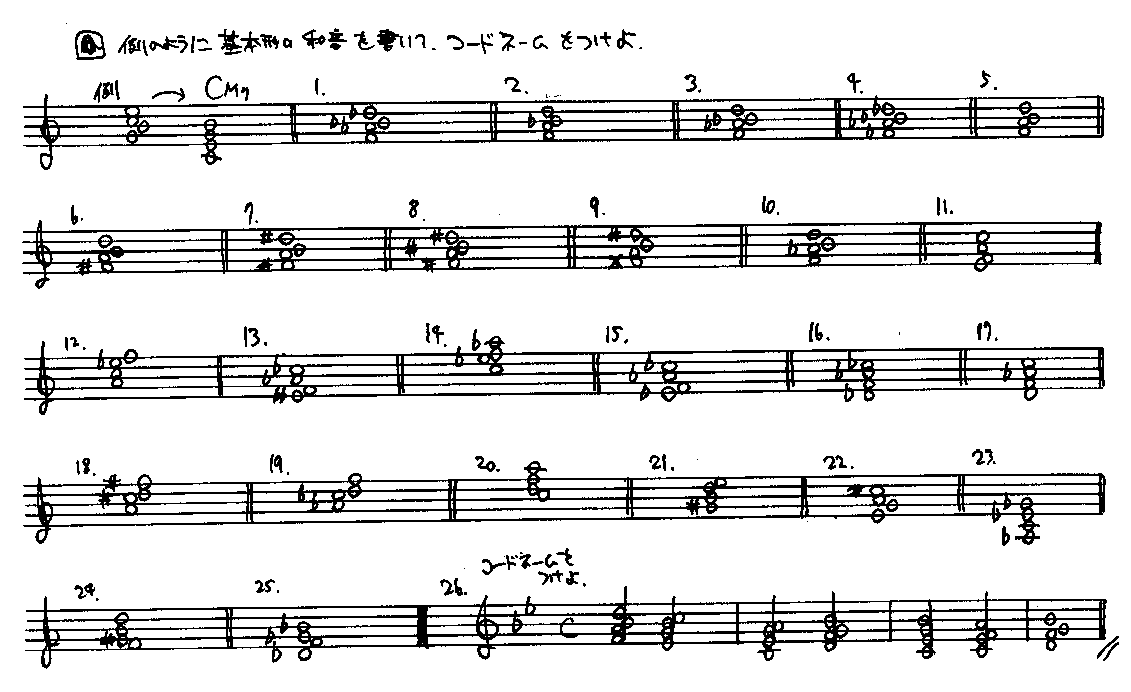
講座(13) 平行調、属調、下属調、同主調、近親調
12音のそれぞれをTonal Centerとしたそれぞれの調性において、ダイアトニックスケールを ドレミのメジャースケールとして長調を定義したが、その調号の枠組みで、ラからそのまま、 ラ-シ-ド-レ-ミ-ファ-ソ-ラと読む、というマイナースケールが存在する。 メジャースケールは1種だが、マイナースケールは多種あり、後述するようにかなり複雑なバリエーションを持つので、 ここからしばらくはダイアトニックメジャースケールをベースとする。 例えば調号としてC mojorの場合、C majorはC-E-Gのドミソで、ここでのラドミはA-C-Eとなり、 これは3和音のコードネームの定義より「Am」(A minor)となる。同じ調性(調号)でのこの、 ドミソとラドミのマイナーとメジャーのセットを、互いに「平行調」と呼ぶ。 調号/調性と、そこでの平行調のセットを列記すると、「(ナシ)-C-Am」「シャープ1個-G-Em」 「シャープ2個-D-Bm」「シャープ3個-A-F#m」「シャープ4個-E-C#m」「シャープ5個-B-G#m」 「シャープ6個-F#-D#m」「フラット1個-F-Dm」「フラット2個-Bb-Gm」「フラット3個-Eb-Cm」 「フラット4個-Ab-Fm」「フラット5個-Db-Bbm」「フラット6個-Gb-Ebm」などとなる。 5度円で、ある調を基準に考えたとき、その右隣、すなわちrootがp5だけ上であるものを「属調」と呼ぶ。 5度円で、ある調を基準に考えたとき、その左隣、すなわちrootがp5だけ下であるものを「下属調」と呼ぶ。 例えば基準としてCという調性を考えると、属調はG、下属調はFである。 いっぽうCという調は、調性「G」の下属調であり、また調性「F」の属調である。 ある調性に注目すると、「自分とその平行調」の2つ、さらに5度円の両隣には、 「属調とその平行調」の2つ、「下属調とその平行調」の2つ、の合計6つの調がある。 これら6個の調を、最初の基準となる調の「近親調」と言う。 一例として「Cm」を考えると、この平行調はEb、また属調Gmの平行調はBb、下属調Fmの平行調はAbとなる。 つまり、Cmあるいは平行調のEbにとって、近親調である「Gm・Bb・Fm・Ab」は特別な関係にある。 どのように特別な関係にあるか、は5線譜に書いてみると一目瞭然である。 Cmあるいは平行調のEbの調号としてフラット3つを書いた5線譜において、とりあえず ドレミファソラと横に並べてみる。シはとりあえずパス。 そして、ドの上に3和音を構成する。ドミソである。Eb-G-Bbとなる。このコードネームはEbである。 次に、レの上に3和音を構成する。レファラである。F-Ab-Cとなる。このコードネームはFmである。 次に、ミの上に3和音を構成する。ミソシである。G-Bb-Dとなる。このコードネームはGmである。 次に、ファの上に3和音を構成する。ファラドである。Ab-C-Ebとなる。このコードネームはAbである。 次に、ソの上に3和音を構成する。ソシレである。Bb-D-Fとなる。このコードネームはBbである。 次に、ラの上に3和音を構成する。ラドミである。C-Eb-Gとなる。このコードネームはCmである。 ここに登場した6つのコードは、元のCm-Ebの近親調として登場した6つと完全に一致する。 これは偶然でなく必然である。 ドからラまでで最後のシだけパスした理由は、シの上に3和音を構成するシレファだけ、 rootと第5音がp5にならない(和音として不完全)からである。このコードは別の役割がある。 これを除くと、ある調のダイアトニックスケールの構成音の上に、臨時記号なしに積み上げた3和音は、 必ず、近親調の6つに対応したコードになる。この和音のグループを、最初の調における ダイアトニックコードと言う。 さて、5度円では離れているものの、ある調と特別な関係の調が1つだけ存在する。 それは、「あるrootのメジャーコードの第3音を半音下げたマイナーコード」およびその逆、という関係である。 これを「同主調」と言う。同じ主音(root)に基づく長調と短調、という意味である。 一例としてC majorを考える。ここではmajorなのでCをドとして、 順に全音レ、全音ミ、半音ファ、全音ソ、全音ラ、全音シ、半音ド、をとると、 C-D-E-F-G-A-B-Cとなる。 次に、C minorを考える。ここではCをスタートのラとして、マイナースケールを 順に全音シ、半音ド、全音レ、全音ミ、半音ファ、全音ソ、全音ラ、ととると、 C-D-Eb-F-G-Ab-Bb-Cとなる。つまり調号としてはフラット3つ、Eb majorという 離れたところにポツンと存在している。同主調も特例として「近親調」と言う。講座(14) 分数コード
コードネームとは、その瞬間に鳴っているコードの構成音を示したもの。 どの構成音をオクターブ上げ下げしても、どの音をどの楽器パートが鳴らしても構わない。 実際には、コードの個々の音をどう配置するか、という「ボイシング」がアレンジの命であるが、 とりあえずはコードネームがあれば、その全ての構成音をどこかのパートで出せばよい。 この例外として、ベースは基本として「それぞれのコードのroot」を鳴らす。 あるいは経過音としてそのコードの5th(rootからp5)を演奏してもよい。 もちろん、ベースなので、音域はオクターブ単位で適正音域に下げる。 ・・・というのが基本原則。この例外として「分数コード」がある。 これは、例えば「Am7/E」とか「Dm7/G」などのように、分数の形式で書かれたコードのこと。 この読み方は、「分子はコード」「分母はベース」である。分数コードがあれば、 ベースは原則としてその分母の音を演奏する。また、ベース以外のパートは分母を無視して、 分子のコードネームの構成音だけを演奏する。 「Am7/A」などというのは意味がないようだが、これはアレンジの要請としてよくある。 分母のベースの動きが重要なので、ベース以外のパートは分子のコードの構成音でない場合には、 基本的に分母の音は鳴らさないこと。講座(15) Diatonic Code (3和音)
5度円で隣接する7つの音、つまりp5により生成される7つの音は、全音音階 Diatonic Scale を構成する。 これを「5つの音」とすればペンタトニックスケールとなるがここではパスしておく。 以降の議論は12音のどれをroot(Tonal Center)としても成立するが、ここでは敢えてC majorを避けて、 調号でシャープ2つのD majorとして話を進める。 楽譜としてD majorのDiatonic Scale、すなわちドレミフィソラシド、すなわちD-E-F#-G-A-B-C#-Dを並べる。 ト音記号の横にはシャープ2つ(FとCの位置)の調号が書かれるので、楽譜の中のF#とC#の音には、 臨時記号のシャープは書かれていないことに注意。 さて、この楽譜でDiatonic Scaleのそれぞれの音をroot(第1音)として、そのまま3度と5度の音を重ねる。 すると、コードネームとしては、この順に、D、Em、F#m、G、A、Bm、C#dim、D、となる。 これらの和音をDiatonic Code (3和音)と言う。 また、Tonal CenterのDを基準にすると、それぞれの和音のrootの音程は、1度から7度なので、 例えばEの上に構成されたEmという和音は、このD majorというキー(調性)において「2の和音」とも言う。 「2の和音」とは、Tonal CenterのrootからDiatonic Scaleで2度の音、つまりEをrootとして、その上に Diatonic Scaleから3度と5度の音を用いるので、Emであり、決してE majorではない。E majorというコードは、 このスケールに無いG#という臨時の音を必要とするので、キーD majorにおいては登場しない。 同様に3の和音はF#m、4の和音はG、5の和音はA、6の和音はBmとなる。 とりあえず7の和音は5度がp5でないのでパスしておく。当然どのキーであっても、 1と4と5の和音はmajorコード、2と3と6の和音はminorコードとなる。 ここまでの単純な事実をまず、手(楽譜・鍵盤)と耳とで確認しておくこと。講座(16) Diatonic Code (4和音)
全音音階 Diatonic Scale の上に、同じスケールの音を構成音として和音を積み上げるというのは、 3和音だけでなく、さらに7度の音を加えた4和音でも成立する。 以降の議論も12音のどれをroot(Tonal Center)としても成立するが、ここでは同様にD majorとして話を進める。 楽譜としてD majorのDiatonic Scale、すなわちドレミフィソラシド、すなわちD-E-F#-G-A-B-C#-Dを並べる。 ト音記号の横にはシャープ2つ(FとCの位置)の調号が書かれるので、楽譜の中のF#とC#の音には、 臨時記号のシャープは書かれていないことに注意。 この楽譜でDiatonic Scaleのそれぞれの音をroot(第1音)として、そのまま3度と5度と7度の音を重ねる。 すると、コードネームとしては、この順に、Dmaj7、Em7、F#m7、Gmaj7、A7、Bm7、C#m7-5、Dmaj7、となる。 これらの和音をDiatonic Code (4和音)と言う。 例えばEの上に構成されたEm7という和音も、このD majorというキー(調性)において「2の和音」とも言う。 「2の和音」とは、Tonal CenterのrootからDiatonic Scaleで2度の音、つまりEをrootとして、その上に Diatonic Scaleから3度と5度と7度の音を用いるので、Em7であり、他のコードにはならない。 例えばEmajor7というコードは、このスケールに無いG#とD#という臨時の音を必要とするので、 キーD majorにおいては登場しない。 同様に3の和音はF#m7、4の和音はGmaj7、5の和音はA7、6の和音はBm7となる。 どのキーであっても、1と4の和音はmajor7thコード、2と3と6の和音はminor7thコード、 そして5の和音だけがドミナント7thコードとなる(←これは重要な事実であると指摘しておく)。 ここまでの事実もまた、手(楽譜・鍵盤)と耳とで確認しておくこと。 クラシックでは3和音までで話をするが、現代であればポップスでもJazzでも、 そしてもちろんクラシックでも適用できるので、今後、和音と言えば原則として4和音であるとする。 3和音は「たまたま7thが省略された、味わいの乏しい和音」として軽く扱えばよい。講座(17) 協和音と不協和音
「和音は4和音だ」と言うと、キー(Tonal Center)の1度の和音は、例えばキーがAであればAmaj7である。 この和音には、A-G#という長7度(半音11個)、展開すればモロに半音という、唸った音程が存在する。 これはクラシック屋に言わせれば「不協和音」となる。 不協和音をいきなり調性の基礎に据えるのは納得いかない、という意見である。 しかし、これはクラシックな感性、ちょっと古臭い感性の苦情なので、軽く無視して構わない。 人類の協和感覚は、音楽の歴史とともに変貌(進化)してきているからである。 旧人類の感覚は放っておいてよい。 もともと音楽の歴史において、最初の楽譜にはユニゾンとオクターブしかなかった。 個々の音はグレゴリオ聖歌のように音階を移動してメロディーを形成するが、 同時に鳴る音は単一(ユニゾン)であるか、あとはオクターブ(男声とボーイソプラノ)だけであった。 これが時代とともに拡張され、豊富な残響のある教会において、直前の音の残響と新しい音とが ハモることから同時に異なる音を鳴らす、というハーモニーの歴史が始まった。 しかし許されたのは、完全5度(p5)と完全4度(p5の展開)とオクターブのみ、という時代が 100年ほど続いた。 その後、イギリスを端緒として後に大陸に伝播し、同時に鳴る和音として「長3度」が登場すると、 音楽の幅は俄然、拡がった。それまでのオクターブとp5とp4は、いわばハーモニーを構成する 無色透明な土台と枠組みとして機能し、ここに色合いとしてmajor(純正な4:5の響き)が活躍した。 さらに50年ほどで、和音はmajorだけでなくminorまで許容され、ときにはドミナント7thの 全音の濁った響きも活用され、バッハの時代に至る。 バッハはp5によって構成される、12音の音体系を縦横に駆使し、スケールから構成される 7度の和音によってp5でない減5度(diminish)音程なども活用した。 しかしまだ、この時代でも調律は純正な音程を求めており、現代の12等分平均律という、 工業生産に適した音律(tuning/temperament)になるまでに200年を要した。 ブルックナー、ワーグナー、マーラーなどにより機能和声の可能性が尽くされると、 12等分平均律において、もはや「3和音」の響きは色合いとして物足りない、と知覚されるようになり、 和音は各種の不協和音程を持つ、4和音の全盛時代となった。ここから現代人の感性までは 繋がっており、現代のポップスでは、メジャーと言えばM7thコード、マイナーであれば m7thコードが基本であり、7thを抜いた単純な3和音はミュージシャンにも嫌われている。 全音のぶつかっている部分が和音としての中心であり、major7thの半音の唸りもまた、 和音としての色合いである。 乳児のうちからこのような音楽ばかりを聞いて育った子供にとって、完全5度の唸らないピュアな 響きはとてつもなく不安で空疎な響きと知覚される。単純なmajorやminorの3和音もまた、 面白くない響きとして知覚される。現在これらは、敢えてpoorな印象を演出するための道具と なっているのである。講座(18) 和音の機能(function)
ここまでの道具だての上で、ようやく「和声」の話が出来る。 あるキー(Tonal Center)を定めると、その音世界において登場するあらゆる和音(コード)には、 それぞれの機能がある。これを感覚での理解とともに議論するのが、本講座の一つの中心である。 ここを理解すれば、アナリーゼ(音楽解析)、アレンジ、アドリブ演奏、そして作曲において、 強力な基礎が出来上がる。 例えば、コードネームとして「Am7」を考えるとして、このコードの機能(音楽的な役割、 意味付け、活用法などなど)は、その音楽のそこでのキー(Tonal Center)によって、 まったく異なっている。調性がC majorの中でのAm7と、調性がDb minorの中でのAm7とでは、 たまたまそのコードは同じ音であっても、コードの意味も、コードを構成するA-C-E-Gの それぞれの音の意味も、まったく違うのである。この理解のためには、キー、調号、 移動ド、などのここまでの準備が全て必要なのである。 さて、何事にも「基準」は必要である。Tonal Centerの1度の和音というのは、 そのキーでの音楽の中心にある。ここがスタートであり、またゴールである。 高さの水準点である。これを「トニック」と呼び、Tonic、記号としてはTで表わす。 機能(function)には、トニックの他にあと2種類しかない。ドミナント(D)とサブドミナント(S)である。 ドミナントとは、「トニックに行きたい!」と切に希求する機能である。 具体的なコードで言えば、あるキーでトニックは1の和音である。 キーをFにすれば、トニックのコードはFM7である。 そしてこの場合のドミナントは、キーのrootに完全5度(p5)下行する和音、 つまり5の和音、C7である。半音で0-4-7-10の音程の和音をドミナント7thと呼ぶが、 これはダイアトニックスケールの枠組みでは5の和音だけに登場した事を確認すること。 ピアノで「(FM7→)C7→FM7」と弾けば、小学校の講堂で「着席」と教わったものと一致する。 つまり、「ドミナント→トニック」の動きは、これで解決した、終了した、安堵した、 という「終止感」をもたらす。この原因については深い音楽的事情があるので、後に議論する。 この「ドミナント→トニック」の動きのことを、ドミナントモーションと言う。 これは音楽を動的に語る上での最大のキーワードである、とここで指摘しておく。 ドミナントモーションを、その連結されたコードのroot(ベース)の動きとして確認すると、 「完全5度下行」あるいは転回して「完全4度上行」である。 これはオクターブ移動によって同じことなので、これを今後「p5」(下行を省略)とする。 さて、次にサブドミナントである。 サブドミナントの位置関係は、「トニック→サブドミナントの関係はドミナントモーションと同じp5である」である。 つまり、トニックのrootからサブドミナントのrootまでがp5の関係、 逆に言えばトニックのrootから完全4度上がサブドミナントのrootである。 キーをFにすれば、トニックのコードはFM7である。 そしてこの場合のサブドミナントは、キーのrootから完全4度上行する和音、 つまり4の和音、Bbmaj7である。 ピアノで「FM7→Bbmaj7→FM7→C7→FM7」と弾けば、小学校の講堂で「起立、礼、着席」と教わったものと一致する。 ときにサブドミナントの機能は「起承転結」の「転」にも例えられる。 ただし音楽のコード進行では、「起承転結」でなく「起承転D結」となり、基本的にはここにドミナントDが入る。 ブルース(ロックンロール、ジャズ)においては、サブドミナントが他のスタイルにない特有のパターン(D→S→T)を持っている(後述)。講座(19) 和音の機能(function)のダイアトニックコードへの拡大
コードの機能は「トニック」「ドミナント」「サブドミナント」の3種類である、と述べた。 一方、7の和音をとりあえず除外して、音楽の枠組みであるダイアトニックスケール上には、 1と4と5のTとDとSの和音だけでなく、2と3と6の和音がある。この機能は何か。 実は、「2はS、3はD、6はT」という等式がある。 例えばキーD majorにおいて、和音は順にDmaj7、Em7、F#m7、Gmaj7、A7、Bm7、C#m7-5、である。 このうち1の和音のDmaj7と6の和音のBm7がトニックである。 また2の和音のEm7と4の和音のGmaj7がサブドミナントである。 また3の和音のF#m7と5の和音のA7がドミナントである。 その理由は、両方のコードの共通音を考えると分かりやすい。 1の和音のDmaj7と6の和音のBm7はD-F#-Aという3音が共通である。 2の和音のEm7と4の和音のGmaj7はG-B-Dという3音が共通である。 3の和音のF#m7と5の和音のA7はA-C#-Eという3音が共通である。 クラシックでは「代理和音」と呼ぶが、代理でもなんでもなく、2の和音は堂々とサブドミナントである。 というより、ポップスとかでは、素のサブドミナント(4の和音)はちょっとストレートで奥ゆかしさがないので、 敢えて薄味の2の和音を使う・・・などの積極的意図がある。 ドミナントモーションは5の和音の方が印象が強いが、敢えてライトタッチな終止感のため、 3の和音でお茶を濁すのもよくある手である(後述)。 トニックの1の和音よりも、平行調の6のマイナー7th和音の中途半端さ(下3音はminorだが上3音がmajor)が 最近はとみに好まれている。 7の和音はもともと強烈な不協和音であるが、強いて分類すればドミナントである。講座(20) マイナースケールの場合(a) Natural Minor Scale
たまたまTonal CenterをCとした場合には、調号に#やbが何も付かない5線譜の上で順に並べた間隔の音、 あるいは鍵盤の白鍵だけの間隔の音、という7つが、12個の音宇宙から選ばれた「ダイアトニックスケール」であった。 そしてこのTonal Centerを「ド」という階名で呼び、ドレミ・・・(長音階Major Scale)となった。 この同じ一群の7音を、スタートライン(root)をラから始めて「ラシドレミファソラ」としたのが、 自然短音階 Natural Minor Scale である。 例えばキーを変えて(移調して)、「Cをラ」としてみる。すると、rootのCのラに対して、 ラシド・・・の音階(階名)の音程は順に上に、 全音シ、半音ド、全音レ、全音ミ、半音ファ、全音ソ、全音ラ、となっているので、 具体的な音名を考えると、C-D-Eb-F-G-Ab-Bb-Cとなる。rootのコードネーム(調性)はCmである。 これはフラット3つの調号、すなわちEb majorと共通であり、 確かにEbはドとなっている。 まず、3和音について、このマイナースケールで構成される和音を考えて、 その機能functionを検討する。 マイナースケールでは、rootはラなので、キーがCm(ハ単調)であれば、Cmが1の和音となる。 同様に、スケール上のそれぞれの音をroot(第1音)として、そのまま3度と5度の音を重ねる。 すると、コードネームとしては、この順に、Cm、Ddim、Eb、Fm、Gm、Ab、Bb、Cm、となる。 1の和音のCmがトニック(T)、4の和音のFmがサブドミナント(S)、 5の和音のGmがドミナント(D)、というのが基本的な機能と言いたいところだが、 実はD機能として働く時には、多くの場合、5の和音の第3音がシャープ(ここではBbのフラットがナチュラルしてBに変化)する、 という特別なケースが発生する(後述)。 つまり、スケール音としてはソはBb音なのに、「ドミナント機能(5の和音)の和音の第3音となる時だけ」ソがB音に半音上がる。 これを「導音」というが、メジャースケールでは最初から導音はrootの半音下なので、特例としての変化は無い。 1と4と5の和音以外の和音の機能を考えるには、3和音でなく4和音にしてみると分かりやすい。 スケール上のそれぞれの音をroot(第1音)として、3度と5度にさらに7度の音を重ねる。 すると、コードネームとしては、この順に、Cm7、Dm7b5、EbM7、Fm7、Gm7、AbM7、Bb7、Cm7、となる。 4和音のうちの3音の共通音を眺めてみれば、 1の和音のCm7と3の和音のEbM7がトニックである。 また4の和音のFm7と6の和音のAbM7がサブドミナントである。 また5の和音のGm7(→G7)と7の和音のBb7がドミナントである。 ここでのドミナントのBb7のBb音は和音単独としては基音なので、シャープ(ナチュラル)したB音にはならない。 なお、混乱を避けるために今後マイナースケールではあまり「○の和音」という言い方をせず、 T/S/Dという機能で考えることにする。講座(21) マイナースケールの場合(b) Harmonic Minor Scale
Natural Minor Scaleでは、スケールを上行しても下行しても、同じ構成音である。 ところがドミナント和音においては、D→T進行でrootに戻るためには、 ドミナント和音に含まれる7音目のソが、rootのラに解決するために「全音上行」しなければならず、 これは地球上を支配する「重力」の影響から、かなりの抵抗感がある。 そこでドミナント和音の例外として、「ドミナント機能の和音の第3音となる時だけソがB音に半音上がる」 という変化をした。耳にしてみれば判るが、キーCm(Eb)であれば「Gm→Cm」に比べて「G7→Cm」の方が、 誰にとってもそれっぽい妥当な和声進行である。 そこで、和音の中での臨時変化だけでなく、いっそのことスケール自体にこの和声進行の性格を反映させよう、 というのが Harmonic Minor Scale である。 例えばキーを「Cをラ」とする。ここでrootのCのラに対して、 ラシドレミファ[ソ#]ラの音階として、 全音シ、半音ド、全音レ、全音ミ、半音ファ、短3度ソ#、半音ラ、となる。 具体的な音名を考えると、C-D-Eb-F-G-Ab-B-Cとなる。 ファとソ#の間隔は、これまで無かった短3度(半音3つ)という異常に大きな間隔である。 これを基本のスケールとしてメロディーなどを作ろう、という体系であり、 この場合には個々の構成音を積み上げて和音を作る・・・という、これまでの枠組みは用いない。 逆に言えば、このスケールを用いた場合には、和声付けについては最初から例外モードに入ったものとして対応する。講座(22) マイナースケールの場合(c) Melodic Minor Scale
メジャースケールの整然とした世界に比べて、マイナースケールでは独特の情感が魅力であるが、 和声進行との兼ね合いで、自然短音階Natural Minor Scaleと、和声短音階Harmonic Minor Scaleとが登場した。 そしてもう一つ(実際にはさらにJazz Minorとかまだまだあるがここでは省略)、 メロディーを重視した、旋律短音階Melodic Minor Scaleがあり、ここまでは理解しておきたい。 和声進行の要請からソがソ#となったため、ファとソ#との音程が半音3個分と広いのが、 メロディーを作る枠組みとしてのHarmonic Minor Scaleの最大の欠点である。 そこで、この拡がった音程を埋めるために、あるいは半音上がったソ#に引っ張られて、 ファもファ#に半音上げた、というのが、「上行」Melodic Minor Scaleである。 例えばキーを「Cをラ」とする。ここでrootのCのラに対して、 ラシドレミ[ファ#][ソ#]ラの音階として、 全音シ、半音ド、全音レ、全音ミ、全音ファ#、全音ソ#、半音ラ、となる。 具体的な音名を考えると、C-D-Eb-F-G-A-B-Cとなる。 個々の音程は半音と全音しかないので、不自然なスキップはなくなるが、 自然短音階からすれば2つの音が臨時にシャープしているスケールである。 実際に鳴らして確認してみると、マイナーというよりかなり明るめの、しかし切ないスケールであり、 いわゆる短調の音楽のメロディーとして普遍的な枠組みである。 そして重要なのは、このスケールは「上行」に使われるものの、「下行」の動きの場合には、 違って来る、という事である。 このスケールのままでラから下行させると、「ラソ#ファ#ミレドシラ」となるが、 これは人間が聞けばほぼ100%、最初の音をラでなくドと知覚して、 「ドシラソファミbレド」となり、前半の5音はマイナーでなくメジャースケールとなってしまう。 そこで、Melodic Minor Scaleでは、上行には「ラシドレミファ#ソ#ラ」を使い、 しかし下行では自然短音階に戻って「ラソファミレドシラ」というように、 動きによってスケールを使い分ける。 当然のこととして、このスケールを用いた場合にも、和声付けは最初から例外モードに入ったものとして対応する。 ここまでの道具だてにより、音楽をメジャーとマイナーとに分けて考えるクラシックの世界から、 メジャーの調性感とマイナーの調性感とが渾然一体となって音楽の和声的構造を作り上げる、という、 ジャズやポップスの世界に入っていくことができる。講座(23) 定番コード進行でLoop音楽はイタダキ
クラシックの和声教科書では、まず「T→S→D→T」とか「T→S→T→D→T」という定番の和声進行(「カデンツァ」と言う)が語られる。 コードネームを付けると、例えばキーをCにすると、「C→F→G→C」とか「CM7→FM7→CM7→G7→CM7」ということになる。 しかし、これはあまり使えない。何故かと言えば、スグに終わってしまうからである。 映像作品やFLASHやゲームのBGMに欲しい音楽は、なんとなく気持ちよく続いてくれる音楽である。 終わりは別にフェイドアウトであってもよい。 そこで多くの場合、Loop Musicが求められている。Loop Musicとは4小節ぐらいの単位で回る音楽「部品」で、 必要であればいくつも連結して使えるように、テンポとキーが統一されている。 MIDIの場合テンポは変わらないので、キーを変えつつ連結していけば、それが和声進行となる。 とりあえずここではクラシック教科書を離れて、このように「使える」ループ音楽の要素として、 コード進行(和声進行)を、具体的な例とともに検討していこう。 ここで紹介する「定番コード進行」とは、そのまま使う単なる事例ではなくて、その背景にある 和声理論的な意味合いを理解すれば、例示されたコード進行だけでなく、 「音楽的に妥当な」オリジナルのコード進行へと自由に発展する、というところがポイントである。講座(24) 定番コード進行[1] カデンツァから循環コードへ
カデンツァの「T→S→D→T」の欠点は、これを繋げるとLoop Musicとしてダサい事にある。 とりあえず今後しばらくは、8ビートないし16ビートで、4小節のループを考える。 つまり、4小節のコードが無限に繰り返される、というルールである。 カデンツァでこれをやると、「T→S→D→T」→「T→S→D→T」→・・・となるが、 4小節目のTと次の1小節目がともにTなので、4小節単位でループしているような盛り上がりが無い。 そこで、切れ目を移動して「T→T→S→D」と変更する。最初のトニックが2小節続いてから、3小節目で「転」となり、 次の小節の頭のTに向かうDがこれに続く。 コードネームを付けると、例えばキーをCにすると「CM7→CM7→FM7→G7」である。 これはとりあえず、聞いてみれば判るが、ようやく使える。 とりあえずこれをパターン(1)と命名する。 「パターン(1) CM7→CM7→FM7→G7」である。 ここでは機能として「T→T→S→D」であるコード進行に限定して、さらに発展させていく。 パターン(1)のコード構成音の中には「B→B→A→G(シシラソ)」が聞こえる。 そこで、これをより自然に「C→B→A→G(ドシラソ)」という動きにすれば、 「パターン(2) C→CM7→FM7→G7」が考えられる。この場合、キーボード奏者は、 2番目のCM7のmajor7thの音に半音上から下りてくるように、コードのC音はオクターブで2音弾く、 というのは自然な感覚である。 このパターン(2)を弾いて確かめたら、ぜひやってみて欲しいのが、 「パターン(3) C→C7→FM7→G7」である。2番目のコードが、CM7でなくドミナント7thコードの C7というちょっと新鮮な和音である。コード構成音の中に聞こえる動きも「C→Bb→A→G」と、 重力の感覚からもより自然である。 これは後述のドミナントモーションによって、次のFM7に強く行きたがる和音なので、 よりコード進行はダイナミックになる。 パターン(1)とパターン(2)は、いずれも構成音が重複しているのでどちらでもいい関係にあるが、 CM7とC7はいずれもトニックでも構成音は不協和の関係にあるので(BとBb)、 パターン(1)とパターン(3)とを同時に(例えば片方をギターが、もう一方をピアノが)演奏することはできない。 4小節のループで1小節目と2小節目が同じ、というのは寂しいので、ここからはパターン(1)は見捨て、 いよいよ次第にポップス的に拡張しよう。 サブドミナントはFM7だけでなくDm7でもある。そこでパターン(2)とパターン(3)のFM7はDm7に置換できる。 これが「パターン(4) C→CM7→Dm7→G7」「パターン(5) C→C7→Dm7→G7」である。 アレンジとしてベースを加えると、この違いが耳で味わえる。 同じ理屈で言えば、今度はドミナントのG7をEm7に置換する、というパターンもあり得る。 ここまでに(2)から(5)まで4通りのパターンが出て来たので、それぞれのG7をEm7に置換すれば さらに4パターンがある。ただし、Em7は機能としてはドミナントに分類されるものの、 後述のドミナントモーションの原動力となるトライトーンを持っていない。一例としてここでは、 「パターン(6) C→C7→FM7→Em7」という1つだけ紹介するが、これはこれで魅力的な響きがある。 最後のEm7から次のループのCに行く、その希求力がちょっと淡白なところが、ある意味では独特の性格である。 逆に、次のループの先頭のドラムにクラッシュシンバルのようなアクセントが欲しい場合には、 これは比較的、弱いので使わない方がいいドミナントである(後に再度検討)。 さて、「T→T→S→D」のパターンの次の展開は、2番目にもう一つのトニック、Am7を使う、というパターンである。 これが人類の歴史上、世界中の津々浦々で定番コード進行となっている「循環コード」そのものである。 サブドミナントにFM7とDm7の両方を例示すれば、 「パターン(7) CM7→Am7→FM7→G7」「パターン(8) CM7→Am7→Dm7→G7」である。 もちろん最初のCM7はCでもよい。このコード進行の場合にはドミナントはG7が一般的である。 鳴らしてみれば一目瞭然、このコード進行の音楽を聞いたことのない人はいないという定番である。 実際の音楽では、ベースラインが最初の2小節で「(C→)B→A」という、重力環境の中でもっとも自然な動きをしている。 さらにパターン(8)の場合には、そうやってCから2小節目にAに着地したベースが、 「A→D→G(→次のC)」という、「p5下行の3段連鎖(!!)」をしている。ここに耳をすませば、 このコード進行の強力なダイナミクスが体感として理解できる筈である。 つまり、循環コードの定番中の定番は、パターン(8)である。 とりあえずこのコード進行を使えば、なんでもOKである。コード進行に著作権は無い。 使えるコード進行はどんどん自分のものとして使いたい。そのための理解である。講座(25) 音楽を駆動するエネルギー原理 - ドミナントモーションの本質
さて、何度も何度も登場している「ドミナントモーション」をここで整理確認する。 ドミナントモーションとは、ドミナントがトニックに解決したい、解決しよう、解決するぞ・・・という 強いエネルギーであり、和声的に音楽を駆動しているダイナミクス原理と言える。 そこでこの原理を、和音の構成音に分解して検討する。 とりあえずキーをCとして、ドミナント和音はG-B-D-FのG7コード、トニックはここではM7thを省略した 素のC-E-GのC majorとする。 まずrootに注目する。「G7→C」の進行のrootはGからCへのp5(ソ→ド)である。 これは前述のように、音組織のもっとも基本的なp5音程の跳躍ということで、rootのp5進行が ドミナントモーションの重要な要素である。 ドミナントモーションに限らず、コード進行、あるいは音楽の中のベースの動きなどで、 とりあえず困った時には「ここでp5進行したらどうか?」と前後の音の候補を探す、というのは、 編曲でも作曲でも定番の候補探索戦略である。 さて、rootのドに対しては、G7のBからCへの半音上行(シ→ド)もある。 これが「導音」である。p5と並んで音楽において自然な進行は、「半音進行」(最小基本単位の推移)である。 そして、Tonicの第3音ミに対しては、G7のFからEへの半音下行(ファ→ミ)もある。 また、第5音のソは、G7とCとの共通音(和音の枠組み)である。 これらの事実から、「G7→C」の動きは、全ての音に「解決」という性格が宿っており、 この進行よりこの機能が強烈な関係の和音は存在しない。 これがドミナントモーションの第一の意味付けである。 ダイアトニックスケールから構成される和音の中で、唯一のドミナント7thコードだったのが、 ここで対象としているドミナント和音だったのを思い出そう。 (7は除外して)他の和音は、例えばCM7、FM7は、下3音がmajor3和音、上3音がminor3和音からなり、 単独でいわば安定している。そしてDm7、Em7、Am7は、上3音がmajor3和音、下3音がminor3和音からなり、 これも単独でいわば安定している。 ところがドミナント7thの和音、ここではG7をよく眺めてみると、 1度と5度は完全5度の枠組みであるが、3度と7度の音は減5度/増4度、 つまり半音6つ分、これは「3全音 - トライトーン」と呼ばれる不協和音程である。 ダイアトニックコード(1から6)の中で唯一、G7だけが和音の内部に不協和音程を持っていることで、 この和音はそれ自身で継続することを拒み、どこかに解決(進行)することを強く希求している。 トライトーンが最小単位の半音の変化で解決されるパターンは次の2つである。 「シ-ファ」の減5度が半音1つずつ狭くなれば「ド-ミ」の長3度に解決する。 「ファ-シ」の増4度が半音1つずつ広くなれば「ミ-ド」の短6度(長3度の転回形)に解決する。 いずれにしても、トライトーンは同時に解決して、人間は無意識ながら、とても嬉しい。 これがドミナントモーションの第二の意味付けである。 さて、ここまでのドミナントは、Tonal CenterのrootであるTonicに対する5のドミナント7th和音、 として見てきたが、ドミナントモーションの本質が「rootのp5進行」「トライトーンの解決」であるとすれば、 ドミナントモーションという原理は、音楽のより広い局面に拡大して活用できる。 例えば、既に紹介した「パターン(3) C→C7→FM7→G7」をもう一度よく眺めてみよう。 ここでは、突然に予告なく2番目のC7(ドミナント7thコード)が登場したが、 実はこれはドミナントモーションの格好の応用例なのである。 C7はドミナント7thコードなので、内部にトライトーンを持ち、自分からrootがp5進行する相手に 対して、強く進行(解決)したいと希求している。その相手こそ、次のFM7である。 つまりこのパターンを応用すると、Tonal Centerにおける位置付けを離れて、あるmajor系の和音に対して、 「そこへrootがp5進行するドミナント7th和音」をその前に持ってくれば、 この進行はかなりイケてる、使える、妥当である、という可能性がとても高いのである。 これがドミナントモーションの第三の意味付けである。この具体例は次にゾロゾロと出て来る。講座(26) 定番コード進行[2] 「II-V」と「Sec.D」
和声進行の機能をここで網羅的に拡張する。 ここまでに見てきたパターン(1)-(8)は、全て後半の2つのコード進行は「S→D」となっている。 このSとDに、例えばキーCとして、FM7→G7を使うと、rootは「全音上行」となるが、これは重力のある地球上では、 ちょっと考えてみればけっこう苦しい動きである。 それに対して、SにDm7を使うと、「S→D」はDm7→G7となって、 rootは「p5の2段連鎖」という、聞き耳を立ててみるとなかなか美しい進行である。 そして、これはTonal CenterのS/Dでの事例に限るものではなく、 より一般的に拡張すれば、「あるドミナント7thコードにrootがp5進行するマイナー7th和音」 という進行は、一般的にかなりイケて、使えて、妥当である。これを「II-V進行」と呼ぶ。 正確には「IIm7-V7」進行であるが、ここでIIとかVという基準のTonal Centerは捨象されていて、 「あるマイナー7thコード → rootがp5進行したドミナント7thコード」と一般化されている点に注意すること。 さて、循環コードの定番と紹介した「パターン(8) CM7→Am7→Dm7→G7」を拡張する。 まず、3番目のDm7をD7にした、「パターン(9) CM7→Am7→D7→G7」を考える。 耳にしてみれば判るが、とても魅力的かつダイナミックである。これは何故か。 理由の一つは、Tonal Centerを離れて、2番目から3番目の進行「Am7→D7」は、まさに「II-V進行」と なっているからである。 また、3番目から4番目の進行「D7→G7」は、後ろのコードG7に対して、上で拡張した意味での ドミナントモーションになっている。この「D7→G7」でのD7のように、 (Tonal Centerとは関係なく)後ろのドミナント7thコードに対してrootがp5で進行する ドミナント7thコードを「セカンダリードミナント(Sec.D)」と言う。 Sec.Dを知ると、コード進行の持ち駒は飛躍的に増加する。 ここでは何より、全体としてはベースは「A→D→G(→次のC)」という、 「p5下行の3段連鎖(!!)」となっている。このパターン(9)は、ダイアトニックコードには登場しない D7というコード(キーCのスケールにおいてF#は登場しない)を含みながら、とても美味しいコード進行なのである。 さて、今度はパターン(8)に対して、2番目のコードAm7を、これもダイアトニックコードには登場しないA7 というコード(キーCのスケールにおいてC#は登場しない)にすると、「パターン(10) C→A7→Dm7→G7」となる。 これは次のDm7はドミナント7thではないのでSec.Dではないが、前述の「拡張されたドミナント7thコード」として 解釈でき、実際に音にしてみるとたまらなく美味しい進行である。後半3つのベースは 同様に「p5下行の3段連鎖(!!)」であり、さらに前半3つのコードに「C→C#→D」という半音上行のメロディーが 隠れている。 そして最後に、これらの合体した「パターン(11) CM7→A7→D7→G7」がある。 解釈すれば、Sec.Dの2連発ということになる。高揚した感じでドミナントモーションが続く、これまた定番の 美味しいコード進行であり、スグにでも使える。 パターンの(8)から(11)を適度に交代しながら繰り返すLoop Musicは、 もはや単調とは言わせない豊富な表情をもった音楽になっているが、 その基本原理はドミナントモーション、II-V、Sec.D、というたった3つの基本ルールだけである。 なお、あらためてパターン(11)を眺めると、和声進行の解釈とは、「後ろから前に説明がつく」ことの連鎖とも言える。 人間は時間とともに音楽を聴取しながら、過去の和声を短期記憶に格納して、新たに到着した和声との繋がりとして (無意識に)認知・解釈・反応している。例えばパターン(11)では、 「C→A7」と進行したA7の瞬間は、前のCと後のA7との関係にちょっと戸惑う。ところが 次に続いたD7により、「A7→D7」のSec.D進行によりナルホドと納得し、ここにさらに G7が続くと、「D7→G7」のSec.D進行、あるいは気付いてみればrootはなんと美しいp5下行の3段連鎖、 そして過去に遡れば最初の3和音に「C→C#→D」という半音上行の美しいメロディーまであった、 そこまで展開していくためのA7なのだった、あぁぁ美しい、と「あと付け」で解釈して、 このコード進行(の余韻、また繰り返されるかもしれない期待)を楽しむのである。 Jazzミュージシャンはそのようなのちのちの効果を意図して、刻々とコードのバリエーションをアドリブで選んで演奏するのである。講座(27) 定番コード進行[3] マイナー基調のコード進行
音楽にはマイナーとメジャーとがあり、混然一体となって和声進行が展開する。 「パターン(1) CM7→CM7→FM7→G7」はメジャーであるかと言うとそれだけではなくて、 CM7とFM7の和音(4和音)は上3音についてはマイナーコードとなっていて、 響きの中にマイナーがある。これを「C→C→F→G7」とやった場合の脳天気さと比べれば、違いは一目瞭然である。 さて、ここでは、「マイナーが主役」というパターンをまとめる事にする。 日本音楽知覚認知学会の村尾先生の報告 によれば、メロディーについて見ると、戦後の歌謡曲は短旋法で作られた唄が非常に多い。 歌謡曲ばかりではなく、明るい未来を歌おうとする「歌声運動」でとりあげられたものもほとんどがロシアを中心とした「短旋法」の曲であった。70年代に入ればこの傾向はいっそう強くなり、金田一春彦が述べたように、音楽に限らず日本人は、憂い、感傷を好む民族だったようである。 ところが、この短旋法を今日のJ-POPのヒット曲から探し出すのは難しい。教科書からも短旋法のメロディーが減少してきている。 日本人の感性の大変化が起きてきたらしい。メロディーからマイナーが減るということは、同時に曲調としてのマイナーが減ることである。 確かにマイナーのコード進行は最近のJ-POPにはなかなか例を見い出しにくいが、アレンジの基本として知っておくことの意味はある。 マイナーについて考えるために、ここでコードは4和音でなく敢えて3和音とする。マイナー7thコードの上3音はメジャーの響きとなるからである。 もっともマイナーの響きを体感するために、ここではキーをAmとして、実際に「パターン(a) Am→Dm→Am→E7」を、 ピアノでもギターでもいいので連続して弾いて体感してみて欲しい。 パターン(a)は機能としては「T→S→T→D」である。前述のように、マイナーであっても、 ドミナントはマイナーコードでなくドミナント7thコードとなる。 そのため、ドミナントの第3音(ここではG#)はシャープする。 この作用から、スケールはHarmonic Minor Scale とかMelodic Minor Scale へと変化した。 さて、パターン(a)の「T→S→T→D」は前述の循環コードなどの流れとは異なるので、 ここで機能を「T→(?)→S→D」というように変えてみる。もっとも単純には「T→T→S→D」として 「パターン(12) Am→Am→Dm→E7」となる。これをまぁ、スタートの基本形とする。 多くの実際の楽曲からこの派生形のパターンを紹介すると、 「パターン(13) Am→C→Dm→E7」 「パターン(14) Am→G→Dm→E7」 「パターン(15) Am→G→F→E7」 「パターン(16) Am→C→D→E7」 などが非常に多い(ぜひ耳で確認して欲しい)。 「パターン(13) Am→C→Dm→E7」の最初の2つ「Am→C」は、平行調の関係にありいずれもTである。 全体としてはマイナーな曲調ながら2番目のコードのメジャー和音で一瞬救われて、 その後に悲しいサブドミナントマイナーに突き落とされる落差が魅力である。 コード進行の内部に「ラドレミ」の上行、あるいは「ラソファミ」の下行が内在するのも定番の由縁かもしれない。 「パターン(14) Am→G→Dm→E7」と「パターン(15) Am→G→F→E7」では、 2番目のコードのrootがスタートから全音下行のメジャーに落下する動きで、 最終的にはドミナントのE7に行くとして、その前にSのDmないしFがある、と解釈される。 特にパターン(15)ではマイナーと言いながら4つのコードのうち3つがメジャーコードであるが、 全体としては立派にマイナーである。 井上陽水の「傘がない」 はコレであり、 そのボーカルに Grand Funk Railroadの"Heart Breaker" のコーラスを重ねた演奏を 高校時代のバンドで行ったことがあるが(判る人はいるのか?(^_^;))、 これは2曲のコード進行が完全に同一でなければ不可能である。そのぐらい定番のコード進行である。 ドミナントにE7を避けてEmを使いながら、パターン(15)で登場する定番コード(Am/G/F)を使った例は無数にあるが、 吉田拓郎の「落陽」 は、「Am→Em→Am→F→G→Am」と後半に重力に逆らって連続全音上昇する力強さが魅力である。 パターン(13)から感覚的にはSec.DのセンスでDmをDとしたのが「パターン(16) Am→C→D→E7」であり、 これも味があるマイナーを醸し出す。 かぐや姫の「あの人の手紙」 はコレである。 要するにマイナーの宝庫と言えばフォークなのである。 パターン(15) と同じように定番なのは、 Chicagoの"25 or 6 to 4" にある「パターン(17) Am→G→Am/F#→[F→E7]」である。 この場合、4小節パターンの最後の1小節が分割されて[F→E7]となる。2番目→3番目のコードはAm7→Am6とも書けるが、 重要なのはベースライン「A→G→F#→[F→E]」である。 なお参考に追加すれば、パターン(15) の「Am→G」の「root全音下行」をメジャーのコード進行に応用した、 「パターン(18) C→Bb→F→G7」という定番もよく使われている。講座(28) 「幻想」のドミナントモーション
和声進行のダイナミクスの鍵となるドミナントモーションをさらにここで拡張する。 マイナーのコード進行の定番として紹介した「パターン(15) Am→G→F→E7」の最後の和音を、 ドミナントのG7に変更すれば「パターン(b) Am→G→F→G7」となる。 一応は妥当であるが、これは最初の3つが3和音なのでバランスが悪い。 そこで最初の3つの和音の下3度にダイアトニックスケールの音を追加して4和音とする。 つまり、4和音の上3音がパターン(b)のコードだ、と解釈すると、「パターン(19) FM7→Em7→Dm7→G7」となる。 これは、使える(実際に多数の楽曲で使われている)し、鍵盤でも弾きやすい。 ところでこのパターンに続いて、セオリー通りにトニックのCM7に「終止」することなく、 このパターンをループとして繰り返しても良好である。そうなるとトニックが登場しないのに、である。これは何故だろうか。 パターン(19)の後半2小節は、II-V進行であり、ドミナントモーションとして次にトニックに行くことを希求している。 また前半3小節のベースが「F→E→D」とシンプルな下行の動きとなっている。 しかしこの4小節ループを繰り返した場合、直前ループの最後のG7から次ループの先頭のFM7のサブドミナントに行く、 という進行はかなり不自然である(そのように注視して聞いてみて欲しい)。 それなのに、この4小節ループの繰り返しは自然で気持ちよい。ここに、ドミナントモーションの第四の意味付けがある。 つまり、ドミナントモーションというのは、実際に次にトニックに解決しなくてもいいのである。 次に解決(終止)するぞ、ベースがp5跳躍するぞ、半音進行(裏5度)するぞ(後述)、 トライトーンが解消するぞ、という「期待感」こそがドミナント原理の本質であり、 実際に次にトニックが来なくても、音楽の流れの中で人間はドミナントモーションの期待感を楽しめるのである。 パターン(19)の場合、FM7に始まりマイナーとメジャーの両方の響きを持つEm7→Dm7の進行から、 II-Vを受けて最後のG7と来ることで、ははぁドミナントだ、いよいよ次はトニック解決するぞ・・・と期待させる。 そして実際にはかなり唐突(不自然)にFM7に進行することで、淡い期待は裏切られて一瞬の浮遊感/フラストレーションがある。 ところがここに、再びパターン(19)のコード進行があると、人間の脳は短期記憶を無意識に再整理して、 なんだこのFM7は不協和音じゃなくてこの進行のスタートラインだったんだ、と解釈して安堵する。 II-VやSec.Dのところで解説したように、人間の和声認知プロセスには、短期・中期・長期の臨時記憶機構と連携して、 その進行を無意識に遡って解釈/説明する機構があり、「あと付け」でも説明できれば、あぁぁそうだったんだ・・・と感嘆できる。 極端な例として、ジャズでピアニストがトニックCM7の後の小節に、うっかり腕がずれてF#M7あたりを弾いてしまったとする。 「CM7→F#M7」は、聴いている方としてはあまりに唐突なコード進行である。 しかしJazz屋は慌てない。ここから例えば、 「CM7→F#M7→F#6→B7→EM7→Em7→A7→DM7→Dm7→Csus4→Db7→C6」とでも弾けば、 人間はコード進行をそれぞれのレベルで逆方向から解釈して、なんだそういう進行の起点だったのか、 とF#M7を許容してしまう(かもしれない)。 ドミナントモーションのこの第四の意味付けは、より広義に解釈すれば、その相手はTonal Centerのトニックである必要はなくなる。 つまり、コード進行の随所において、その局所的な(仮想)目標点に対して、ドミナントモーションで進行する、と期待させる コード進行があれば良い。これは実際にその(仮想)目標点に進行しない「幻想」であっても良いのである。この原理を理解すると、 コード進行の自由度は大幅に拡大してくる。Jazzのインプロ(即興)のセンスの入口である。講座(29) 定番コード進行[4] 裏5度 (Sub.D)、半音下行
クラシックのドミナントはトニックのp5上、とあるが、Jazz屋のドミナントはこれだけでなく、 「トニックの半音上」も同等にドミナントである。これを「裏5度」と言い、Sub.Dと記述する。 例えばキーがC majorであれば、古典的なドミナントはG7である。 そしてこの裏5度は、5度円でG7のちょうど反対側、rootはトライトーン(3全音、6半音)だけ離れたC#/Dbなので、 コードネームとしてはC#7/Db7である。 ドミナントモーションの図式としては、古典的な「G7→C」のSub.Dとしては、「C#7→C」ないし「Db7→C」となる。 最後のCはCM7でも、あるいはよくあるC6でも構わない。maj7thも6thも9thも、ちょっとした味付けである。 要するに「rootの半音上のドミナント7th」である。 5度円の説明をした時に、12音から順に作用させて12個の音の連鎖を生成するのは、完全5度p5と、 あとは基本単位の半音しかない(他は裏返し/逆回りとして等価)、と述べた。 その「p5」と「半音」とが、ここで晴れて対等に並ぶこととなった。 さて、ではどうしてSub.Dもドミナントなのか、これは構成音を調べてみれば明白である。 キーをCとしたまま、ドミナントのG7を眺めると、「G-Dの完全5度と、B-Fのトライトーン」からなる。 ところでSub.DのC#7/Db7を眺めると、「C#-G#/Db-Abの完全5度と、B-Fのトライトーン」からなる。 つまりこの2つのコードに共通するのは、「B-Fのトライトーン」+「(協和する)完全5度音程」である。 そして前述のように、「B-Fのトライトーン」こそ、キーCにおけるドミナントモーションの存在理由であった。 完全5度の枠組みというのはそれ自体の色彩は無色透明であり、色はトライトーンが付けている。 これがDとSub.Dとで完全に共通であるために、両者は正当なドミナントなのである。 G7は、Cへの解決の際にrootがp5跳躍という爽快さを持つが、ボイシングを変えた場合、 「G→G」という面白くない共通音となる可能性も秘めている。 一方、Sub.DのC#7/Db7では、C#-G#/Db-Abの完全5度はroot(Tonal Center)に対して、 いずれも半音ずつズルッと下行することで解決する。どうやってもズルッと半音下行する。 これはp5ジャンプの解決に比べてある意味では色っぽい(Jazzっぽい)動きであり、 Jazz屋はむしろこちらを優先することも多い。 C#7/Db7は同じコードなのでここではDb7として、前述の循環コードのドミナントG7をSub.Dにすると、 パターン(8)は「パターン(20) CM7→Am7→Dm7→Db7」に、 パターン(9)は「パターン(21) CM7→Am7→D7→Db7」に、 パターン(10) は「パターン(21) C→A7→Dm7→Db7」に、 パターン(11) は「パターン(22) CM7→A7→D7→Db7」になる。 次の小節にはC/C6/CM7/C9など、どれに続いても構わない。 いずれも音で確認してみて欲しい。 また、ベースの半音下行の動きの気持ち良さに固執すれば、長さとしてはやや不整脈となるので調整を必要とするが サブドミナントFM7からトニックのCM7まで連続半音下行を貫いて、 「パターン(23) FM7→Em7→EbM7→Dm7→Db7(→C6)」のようなコード進行もよく使われる。 この途中のどこかのコードにSec.Dの関係などでジャンプ合流するパターンを試してみると、 例えば「パターン(24) Bb7→EbM7→Dm7→Db7」など、 デタラメでなくコード進行として妥当なバリエーションは飛躍的に増えることになる。講座(30) 定番コード進行[5] ブルース進行 (その1)
ここでは配布資料の"Examples of BLUES Progression"(in the Key of F)に従って、17種類のサンプルのうち、 前半の9パターンを検討する。 "NOTE:"にあるように、これらのパターンは結び付けたり細かいバリエーシヨンを作り出すことで、 何百種類にも拡張できる。ブルース進行であるための条件はシンプルであり、全体が12小節からなり、 基本は「最初の4小節はトニック」「続く4小節はトニックに進行するサブドミナント2小節とトニック2小節」 「最後の4小節の1小節目はドミナント(ここにII-Vというのもアリ)、次の2小節目がサブドミナント(ここもドミナントというのもアリ)」、ということである。 番号を揃えるためにここまでの「パターン(n)」とは別に、「ブルース(n)」という言い方をする。 ブルースというのはあくまでパターンの象徴であり、既述のようにロックンロールもバラードの多くも、 この進行そのものである。 「ブルース(1) F7→F7→F7→F7→Bb7→Bb7→F7→F7→C7→C7→F7→F7」は、"NOTE"にあったブルース進行の 定義のまず基本形である。最後の4小節に、前述の「D→S→T」が無いが、これもブルースである。 「ブルース(2) F7→F7→F7→F7→Bb7→Bb7→F7→F7→C7→Bb7→F7→C7」は、もっとも教科書的な定番ブルース進行 そのものとなっている。最後の4小節が、「D→S→T→D」となり、次の12小節パターンに繰り返す動きが強化されている。 「ブルース(3) F7→Bb7→F7→F7→Bb7→Bb7→F7→F7→G7→C7→F7→C7」は、単調だった冒頭4小節の2小節目に、 チラッとSに動いて戻り(この動きも定番)、後半ではブルース(2)のパターンと9-10小節が異なっている。 ドミナントのC7に繋がるG7は、とても美味しいSec.Dである。 「ブルース(4) F7→Bb7→F7→F7→Bb7→Bb7→F7→D7→G7→C7→F7→C7」は、ブルース(3)との違いは8小節のD7だけである。 これは、Sec.DのG7にさらにSec.DであるD7から進行する、というもので、ブルースの12小節の流れの頂点である 9小節目付近に最大の盛り上がりを演出する定番である。 ここから以降は、1小節内でコードがさらに分割して進行するので、1小節分のコードをスラッシュで分割して記述する。 これは、スラッシュの右側(分母)もコードネームなので「分数コード」ではない。ここでの解説だけのための特別な記法なので注意されたい。 「ブルース(5) F7→Bb7→F7→F7→Bb7→Bb7→F7→D7→Gm7→C7→F7→Gm7/C7」は、 ブルース(6)との違いが最後の4小節だけにある。9小節目のGm7は、次のC7に対して「II-V」と解釈できる。 そして12小節目のドミナントが、半分の長さの「II-V」に分割されているが、これも定番のパターンである。 「ブルース(6) F7→Bb7→F7→F7→Bb7→Eb7→F7→D7→Db7→C7→F7→Db7/C7」は、 6小節目で、それまでのパターンでは2小節続いたサブドミナントから変えてEb7が入っている。 これはBb7の連続でなく、前のBb7をSec.Dと感じての進行であり、続くF7への全音上行がかなり強いパワーを与える。 9小節目は、その前のD7と後のC7との間を半音進行で繋ぐSub.D(裏5度)の教科書的パターンである。 最後の12小節目の「Db7/C7」も、ブルース(5)の最後の「Gm7/C7」のちょうど裏5度の半音進行である。 「ブルース(7) F7→Bb7→F7→Cm7/F7→Bb7→Eb7→F7→Am7/D7→Gm7→C7→Am7/D7→Gm7/C7」は、 ブルース(5)をベースとして、1小節を「II-V」で2分割するパターンの展示会のような定番が並んでいる。 まず4小節目のトニックを「Cm7/F7」と「II-V」に分割。8小節目のSec.DのD7を「Am7/D7」とこれまた「II-V」に分割。 11小節目のトニックF7は、12小節目の「Gm7/C7」のGm7に繋がるドミナントD7を「Am7/D7」とまたまた「II-V」に分割している。 「ブルース(8) F7→Bb7→F7→Cm7/F7→Bb7→Eb7→Am7→D7→Gm7→C7→Am7/D7→Gm7/C7」は、 中間ブロック(5-8小節)のバリエーションを含めて、12小節の進行のテンポ感が発展している。 最初の6小節と最後の4小節はブルース(7) と一致するが、7-8小節の「Am7→D7」は、ブルース(7)では8小節目にギュッと圧縮されていた 「II-V」進行であり、この中間ブロック(5-8小節)は5小節目のBb7以外、全てバリエーションの和音(スケールに無い音を含む和音)となって、 小節内のコード分割もない長時間スケールで、ラテン系の明るさのある味わい深い進行が続く。 「ブルース(9) F7→Bb7→F7→Cm7/F7→Bb7→Bm7/E7→F7/E7→Eb7/D7→Gm7→C7/Bb7→Am7/D7→Gm7/C7」は、 逆に小節内のコード分割の連続でインパクトのある進行である。 最初の5小節と最後の2小節はブルース(8) と一致するが、6-8小節の流れは半音進行を強調したものである。 Bb7に続く6小節目の「Bm7/E7」は、root半音上行に続く「II-V」で、その次のF7には半音上行でもちょっと難がある。 ところが7-8小節が、9小節目のGm7に向かって「F7→E7→Eb7→D7(→Gm7)」と、パターン(23) に通じるような半音下行の連鎖で、 テンションの高い中間ブロック(5-8小節)となっている。 10小節目が分割されて「C7/Bb7」と後半にBb7が出るのは、次のAm7へのSub.D(裏進行)である。講座(31) 小節内の分割によるコード進行のバリエーション拡大
上のブルース進行(1)の例の中に、基本としては1小節1コードであるシステムの中で、 Sec.DやII-VやSub.Dなどを交えて、1小節が2コードに分割される例が登場した。 これはコード進行をオリジナルにアレンジする上で重要なバリエーションであり、個々には理論的な説明が成立するので、 音楽的な解釈として、つまり聞いている人間にとって、自然であり、妥当なコードとして許容/歓迎される。 もちろん、定番の循環コード「パターン(8) CM7→Am7→Dm7→G7」にも、この1小節を2分割したアレンジは適用できる。 例えば4小節全体の中で2小節目を分割するとすれば、3小節目のDm7に対するSec.DはA7なので 「パターン(25) CM7→Am7/A7→Dm7→G7」となる。 これは2小節目内の「Am7→A7」が「C→C#」と半音上行で盛り上がるので、もちろん妥当である。 あるいは3小節目のDm7に進行するSec.DのA7に対して、2小節目の前半のコードもさらにSec.Dとするなら、 「パターン(26) CM7→E7/A7→Dm7→G7」となる。 パターン(26)は冒頭の2つのコードの関係にやや当惑するが、以降の進行により問題なく納得してしまう。 この2つの例では、4小節パターンの2小節目を分割してみたが、後半の3-4小節の「Dm7→G7」の「II-V」は、 これを圧縮して4小節目に持っていくことも可能である(というか、これは非常に多い)。 すると、「パターン(c) CM7→○→◇→Dm7/G7」という図式になる。 なお、最後のG7を裏コードに半音進行する「パターン(d) CM7→○→◇→Dm7/Db7」にも展開できるので、 バリエーションはこの2倍ある事になる。 コードは「あと付け」で後ろから付けていくと簡単なので、パターン(c)の3小節目の◇についてまず検討しよう。 次のDm7に進むコードとしては、ドミナントのA7が第一候補である。 そのA7に「II-V」で進むコードはEm7、Sec.Dで進むコードはE7である。つまり、 「パターン(e) CM7→○→Em7/A7→Dm7/G7」または「パターン(f) CM7→○→E7/A7→Dm7/G7」となり、 例えば標準的な循環コードの2小節目のAm7を○のところに入れた、 「パターン(27) CM7→Am7→Em7/A7→Dm7/G7」「パターン(28) CM7→Am7→E7/A7→Dm7/G7」 はとりあえず、立派に使えるコード進行(循環コードのバリエーション)となっている。 また、3小節目のEm7やE7に進行するSec.DとしてB7を登場させれば、この2つは 「パターン(29) CM7→B7→Em7/A7→Dm7/G7」「パターン(30) CM7→B7→E7/A7→Dm7/G7」 となり、冒頭の2つのコードの関係にかなり当惑するが、これまた以降の進行により問題なく納得してしまう。 このB7の唐突さとそれが1小節マルマル続く浮遊感を解決するには、B7を2小節目の後半となるように分割して、 理由(意味)のあるコードを前半に据えればよい。 B7に「II-V」で進むコードはF#m7、Sec.Dで進むコードはF#7である。 これらのコードのrootのF#とは、TonicのCの5度円の反対側、つまりもっとも遠い音である。 CM7からこのコードに進行するだけでは、耳で聞いてもとうてい納得できない違和感がある。 ところが、次々にコード進行することであと付けの解釈が成立する場合、 冒頭の違和感は「高いテンション」と見直されてOKということになり、 「パターン(31) CM7→F#m7/B7→Em7/A7→Dm7/G7」 「パターン(32) CM7→F#7/B7→Em7/A7→Dm7/G7」 「パターン(33) CM7→F#m7/B7→E7/A7→Dm7/G7」 「パターン(34) CM7→F#7/B7→E7/A7→Dm7/G7」 と一気に2*2=4通りの「使える」コード進行が生まれる。 ちなみに、この最後の「Dm7→G7」は、Sec.DのD7によって「D7→G7」としてもいいので、 さらにバリエーションは倍々ゲームで増えることに注意しよう。 このように、循環コードに限ったことではなく、あらゆるコード進行は、 その小節内を分割した2つのコードというアレンジを受け入れてくれる。講座(32) コードをまたぐドミナントモーション
小節内を分割して一気に増えた「使える」コード進行のアレンジであるが、 ここではバリエーションの可能性をさらに飛躍的に増大させる理論を追加する。 基本は既に紹介した、コードを知覚・認知する人間の脳の働きである。 [再録]人間の和声認知プロセスには、短期・中期・長期の臨時記憶機構と連携して、 その進行を無意識に遡って解釈/説明する機構があり、「あと付け」でも説明できれば、あぁぁそうだったんだ・・・と感嘆できる。 この作用の一つとして、Jazzコード理論に登場するのが、「コードをまたぐコード進行」である。 ここまでの説明では、あるコードに進行する「前の」コードとは、「直前」であった。 しかし、人間の崇高な脳機能は、「直前」のコードだけでなく、「もう1つ前」のコードへの進行を、 納得するコード進行の理由付けとして解釈してくれる場合がある。 それは、コード進行の関係の原理が、 広義のドミナントモーション(II-V、Sec.D、Sub.Dなども含まれる)という音楽的ダイナミクスの場合である。 これを、文献によっては 拡張ドミナント(Ext.D) と言う( ※ 文献によっては、「ダイアトニックコードに進行するNDCのドミナント7thコードのみをSec.Dと呼んで、それ以外の全てのNDCに進行するNDCのドミナント7thコードをExt.Dと呼ぶ」という説もあるが、本稿では上記の立場をとる )。 一例として、ここでは「パターン(c) CM7→○→◇→Dm7/G7」をスタートラインとしてみる。 ◇の部分に、直後のDm7でなく、これをまたいでG7に進行するSec.DのD7を置くことはOKである。 もっともシンプルには、○にAm7を入れて 「パターン(35) CM7→Am7→D7→Dm7/G7」 となる。「D7→Dm7」の部分だけを見ると、なんでドミナント7thコードから、 同じrootのマイナー7thに行くのか分かりにくいが、実は文脈は「D7→(パス)→G7」という進行なのである。 さらにパターン(35)の3小節目を分割して、II-Vで「D7」を「Am7→D7」とすると、 これは2小節目のAm7とかぶってしまう。 そこで2小節目を、これまたAm7をまたいでD7に進行するSec.DのA7と、そこにII-V進行するEm7を置くと、 「パターン(36) CM7→Em7/A7→Am7/D7→Dm7/G7」 となる。音にしてみるとなかなか味のあるコード進行であり、もちろん活用できる。 広義のドミナントモーションには裏5度/半音進行があるので、ちょっと聞くと無茶なようでも、 例えば一瞬、転調のように(かなり不自然に)聞こえる 「パターン(37) CM7→F7/Bb7→A7/D7→Dm7/G7」 なども、繰り替えしてみると馴染んできてしまう。色々と試してみよう。講座(33) 定番コード進行[6] ブルース進行 (その2)
ここでは配布資料の"Examples of BLUES Progression"(in the Key of F)の17種類のサンプルのうち、 後半の8パターンを検討する。 ここからは先頭のコードがF7でなくFM7と、これまでの例よりも冒頭トニックとしての安定感が高くスタートする。 「ブルース(10) FM7→Em7/A7→Dm7/G7→Cm7/F7→Bb7→Bdim7→Am7→Abm7/Db7→Gm7/C7→Dbm7/Gb7→F7/D7→Gm7/C7」は、 最初の4小節内の前半コードが「ドシラソ」と下行(最初の4小節内の後半コードは「ソミレド」と下行)しつつ、 ダイナミックな「II-V」の3段連発となってスタートする。 中盤の5-8小節は「Bb7→Bdim7→Am7→Abm7/Db7」はdim 7thコードを交えた半音進行と裏5度、 そして最後の4小節もII-Vと裏5度でもうハチャメチャであるが(これは弾き難い)、個々に理由がある進行である。 「ブルース(11) FM7→Em7/Ebm7→Dm7/Dbm7→Cm7/Cb7→BbM7→Bbm7→Am7→Abm7→Gm7→C7→Am7/Abm7→Gm7/Gb」からは、5小節目のサブドミナントもBbM7となったパターン例である。 ここでは冒頭の4小節に、これでもかとminor7thコードの半音下行進行を重ね、 逆に中間部の5-8小節は分割しない長さでシンプルな半音下行進行、 そして最終ブロックも最後の2小節にシンプルな半音下行進行(裏コード)と徹底している。 ここから一部をアレンジした 「ブルース(12) FM7→BbM7→Am7/Gm7→Gbm7/Cb7→BbM7→Bbm7→Am7→Abm7→Gm7→Gb7→FM7/Abm7→Gm7/Gb」 では、4小節の後半の半音進行をp5に、逆に10小節目のp5を裏コードの半音進行としている。 よく似た 「ブルース(13) FM7→BbM7→Am7/Gm7→Gbm7/Cb7→BbM7→Bbm7/Eb7→AbM7→Abm7/Db7→Gm7/C7→Gb7→Am7/Abm7→Dbm7/Gb」となっていて、6-7小節目、あるいは9小節目にバリエーション例が見える。 残りは4例であるが、もはやヤケクソのようにあれこれバリエーションが展開されている。 ここではコードを再録するにとどめるので、実際に音にして比べて欲しい。 「ブルース(14) FM7→Em7/A7→Dm7/Gm7→Cm7/F7→BbM7→Bbm7/Eb7→Am7→Abm7/Db7→Gm7→C7→Am7/D7→Gm7/C7」 「ブルース(15) FM7→Em7/A7→Dm7/Gm7→Gbm7/Cb7→BbM7→Bbm7/E7→Am7→Abm7/Db7→Gm7→C7/Bb7→Am7/D7→Gm7/C7」 「ブルース(16) F#m7/B7→Em7/A7→Dm7/Gm7→Cm7/F7→BbM7→Bbm7/Eb7→AbM7→Abm7/Db7→GbM7→Gm7/C7→Am7/D7→Gm7/C7」 「ブルース(17) FM7→F#m7/B7→EM7/EbM7→DbM7/BM7→BbM7→Bbm7/E7→AM7→Am7/D7→GM7→GbM7→FM7/AbM7→GM7/Gb」 特にブルース(16)では、いちばん最初のコードがトニックでなく、 「F#m7/B7→Em7/A7→Dm7/Gm7→Cm7/F7」という4段連続の「II-V」とSec.Dの連続技であり、 これが5小節目のBbM7に続くことでようやくテンションの解決を見るパターンである。 これらブルース進行17パターンに登場したコードネームは、とても"in the Key of F"とは思えないコードも多数、見つけることができる。 つまり、どのようなキーであっても、どんなコードを演奏しても、「間違い」でないように進行させることが可能である、 という事実を理解したい。ただし、でたらめなコードを前後関係の助けなしに適当に配置しても、それは不自然だったり ダサイものになったりするのである。 コードはdynamicに感じるものであり、決してstaticに接してはいけないのである。講座(34) ドミナントモーションの順列組合せ→FMC3
ブルース進行の12小節から再び4小節のLoop Musicに戻って、ここで「使える」4小節単位のコード進行の一例として、 ある一群のコード進行の可能な組合せを数学的に網羅してみよう(1小節目のコードについて無条件であることに注意)。 これは、FMC3の自動作曲エンジンの一つの中枢ともなっているので、 興味のある人はぜひ参照して欲しい。まとめると以下になる。 まず、「コード進行のルール1」として、 4小節のコード進行は、「前2小節のパターン」と「後2小節のパターン」とを連結する。 次に「コード進行のルール2」として、 前半の「2小節パターン」において、後ろのコードは必ずドミナント7thコードとし、 前のコードは「ドミナント7th(Secondly Dominant: II7→V7)かマイナー7th(IIm7→V7)のいずれか」とする。 ここでrootは「p5下行か半音下行(裏5度)のいずれか」の2通りで進行する。 これにより2*2=4通りのパターンがある。 さらに「コード進行のルール3」として、4小節のうち前2小節と後2小節のパターンを連結するルールは、 「ルール (3A) 前2小節の後半のコードから後2小節の前半のコードへの隣接進行」 「ルール (3B) 前2小節の後半のコードから後2小節の後半のコードへの進行(Ext.D)」 のいずれかであるとする。 ここでrootは「p5下行か半音下行(裏5度)のいずれか」の2通りで進行する。 さらに「コード進行のルール4」として、 後半の「2小節パターン」において、後ろのコードも必ずドミナント7thコードとする。 「○→Vm7」という進行はここでは採用しないので、 ルール(3A)の場合には前のコードはマイナー7thは採用されず必ずドミナント7thとする。 これにより、4*2=8通りのパターンがある。 最後に「コード進行のルール5」として、 後半の「2小節パターン」において、ルール(3B)の場合には、前のコードも「ドミナント7thかマイナー7thのいずれか」の2通りがある。 これにより、4*2*2=16通りのパターンがある。以上を組み合わせると、(A)(B)合わせて計24パターンのコード進行が生成できる。 具体的には、キーをC majorとすると、最後の4小節目のコードはTonal Centerに対するドミナントなので、 必ずG7かDb7となり、パターンは以下のようになる。 「パターン(38) Em7→A7→Dm7→G7」 「パターン(39) E7→A7→Dm7→G7」 「パターン(40) Em7→A7→Dm7→Db7」 「パターン(41) E7→A7→Dm7→Db7」 「パターン(42) Em7→A7→D7→G7」 「パターン(43) E7→A7→D7→G7」 「パターン(44) Em7→A7→D7→Db7」 「パターン(45) E7→A7→D7→Db7」 「パターン(46) Bbm7→Eb7→D7→G7」 「パターン(47) Bb7→Eb7→D7→G7」 「パターン(48) Bbm7→Eb7→D7→Db7」 「パターン(49) Bb7→Eb7→D7→Db7」 「パターン(50) Am7→D7→Dm7→G7」 「パターン(51) A7→D7→Dm7→G7」 「パターン(52) Am7→D7→Dm7→Db7」 「パターン(53) A7→D7→Dm7→Db7」 「パターン(56) Ebm7→Ab7→Dm7→G7」 「パターン(57) Eb7→Ab7→Dm7→G7」 「パターン(58) Ebm7→Ab7→Dm7→Db7」 「パターン(59) Eb7→Ab7→Dm7→Db7」 「パターン(60) Ebm7→Ab7→D7→G7」 「パターン(61) Eb7→Ab7→D7→G7」 「パターン(62) Ebm7→Ab7→D7→Db7」 「パターン(63) Eb7→Ab7→D7→Db7」 新しい4小節ループに進行した場合、Tonal Centerをランダムに12音から変えてもよい、 というのは、これまでの音楽理論からちょっとだけ踏み出した、FMC3での提案である。講座(35) FMC3は実はもっと拡張できた(^_^)
◆コード進行パターン「T→T→S→D」のケーデンスから (Key=C) - 20通り 「C→CM7→FM7→G7」 1-2小節目で変化させるためトライアドを用いた進行 「C→C7→FM7→G7」 「CM7→C7→FM7→G7」 2小節目のCM7の代わりにノンダイアトニックコードのC7を用いた進行。C7→FM7がSec.Dとなっている 「C→CM7→Dm7→G7」 「C→C7→Dm7→G7」 3小節目のFM7の代わりにDm7を用いた進行。Dm7→G7はツーファイブなのでFM7よりさらに良好 「CM7→Am7→FM7→G7」 「C→Am7→FM7→G7」 2小節目のCM7の代わりにAm7を用いた進行 「CM7→Am7→Dm7→G7」 「C→Am7→Dm7→G7」 3小節目のFM7の代わりにDm7を用いた進行。循環コードと呼ばれる。後半2小節がツーファイブ、 2→3小節はドミナントモーションではないがrootがp5下行なので無難に良好 「CM7→Am7→D7→G7」 循環コードの3小節目のDm7の代わりにノンダイアトニックコードのD7を用いた進行。 Am7→D7がツーファイブ、D7→G7がSec.Dとなっている 「CM7→A7→Dm7→G7」 循環コードの2小節目のAm7の代わりにノンダイアトニックコードのA7を用いた進行。 CM7→A7→Dm7にC→C#→Dという半音上行の進行が含まれ、A7→Dm7がSec.Dとなっている 「CM7→A7→D7→G7」 循環コードの2小節目のAm7の代わりにノンダイアトニックコードのA7を、3小節目のDm7の代わりに ノンダイアトニックコードのD7を用いた進行。 A7→D7→G7がSec.Dの2連発になっている。ドミナントセブンスコードばかりでm7が無くあまりに明るい(^_^;) 「CM7→Am7→Dm7→Db7」 「CM7→Am7→D7→Db7」 「CM7→A7→Dm7→Db7」 「CM7→A7→D7→Db7」 循環コードから派生した上の4パターンの4小節目のG7の代わりに、裏5度(Sub.D)であるDb7を用いた進行 「Am7→CM7→FM7→G7」 1小節目のCM7の代わりに同じトニックのAm7を用いた進行。最後の4小節目は必ずドミナントのG7か その裏のDb7であり、その「戻り先」として期待される1小節目はトニックのAm7もOK 「C→Bb→F→G7」 「FM7→Em7→Dm7→G7」 「Bb7→EbM7→Dm7→Db7」 マイナー基調/幻想のドミンナトモーションの経験則からこれらもOK ※ この講座の最後の「講座(34) ドミナントモーションの順列組合せ→FMC3」 ※ には抜けがあり、まだまだ多くの妥当なコード進行がある、と判明したので(^_^;)、以下に整理する。 ◆FMC3のコード進行から (Key=C) - 112通り FMC3は4小節ループごとに転調することを前提としているので上述を拡張している。 Key=Cとすると、4小節目は必ずドミナントのG7かその裏のDb7。1小節目は転調直後なので何でもOK。 あるコードから、後に解釈できる妥当なコード進行の関係で4小節が進行していけば音楽的にOK、という理論。 以下のルールを定めて全ての組み合わせを網羅する。 ・4小節のコード進行は、「前2小節のパターン」と「後2小節のパターン」とを連結する ・前後それぞれの「2小節パターン」において、後ろのコードは必ずドミナント7thコードとする ・それぞれの「2小節パターン」において、前のコードは「ドミナント7th(II7→V7)か マイナー7th(IIm7→V7)のいずれか」とする このrootは「完全5度下行か半音下行(裏5度進行)のいずれか」の2通りで進行する ・「前2小節のパターン」と「後2小節のパターン」とを連結する関係は以下のいずれか 前2小節の後ろのコードと,後2小節の前のコードを隣接進行Sec.Dで連結 前2小節の後ろのコードと,後2小節の後ろのコードをExt.Dで連結 このrootは「完全5度下行か半音下行(裏5度進行)のいずれか」の2通りで進行する G7に進むのは、Dm7とD7(p5下行)と、Ab7とAbm7(半音下行)。 Db7に進むのは、Abm7とAb7(p5下行)と、D7とDm7(半音下行)。 ここまでで組み合わせは以下の2×4=8通り。 Dm7→G7 D7→G7 Ab7→G7 Abm7→G7 Abm7→Db7 Ab7→Db7 D7→Db7 Dm7→Db7 ここから前2小節との連結は以下のいずれか。 ・前半2小節の後のコードからExt.Dで後半2小節の後のコードに進む ・前半2小節の後のコードからSec.Dで後半2小節の前のコードに進む ●前半2小節の後のコードからExt.Dで後半2小節の後のコードに進む場合 後半2小節の後のコード(4小節目のコード)がG7の場合 □→D7→◇→G7 □→Ab7→◇→G7 ◇にその直前と同じコードが入るものは除外するので、以下の6つだけが候補となる □→D7→Dm7→G7 □→D7→Ab7→G7 □→D7→Abm7→G7 □→Ab7→Dm7→G7 □→Ab7→D7→G7 □→Ab7→Abm7→G7 この□の部分(1小節目のコード)に、続くコードに対してII-VとSec.Dの各2通りが入る(p5下行と半音下行) ので、以下の24通りが全てOKとなる 「A7→D7→Dm7→G7」 「Am7→D7→Dm7→G7」 「Eb7→D7→Dm7→G7」 「Ebm→D7→Dm7→G7」 「A7→D7→Ab7→G7」 「Am7→D7→Ab7→G7」 「Eb7→D7→Ab7→G7」 「Ebm7→D7→Ab7→G7」 「A7→D7→Abm7→G7」 「Am7→D7→Abm7→G7」 「Eb7→D7→Abm7→G7」 「Ebm7→D7→Abm7→G7」 「A7→Ab7→Dm7→G7」 「Am7→Ab7→Dm7→G7」 「Eb7→Ab7→Dm7→G7」 「Ebm7→Ab7→Dm7→G7」 「A7→Ab7→D7→G7」 「Am7→Ab7→D7→G7」 「Eb7→Ab7→D7→G7」 「Ebm7→Ab7→D7→G7」 「A7→Ab7→Abm7→G7」 「Am7→Ab7→Abm7→G7」 「Eb7→Ab7→Abm7→G7」 「Ebm7→Ab7→Abm7→G7」 後半2小節の後のコード(4小節目のコード)がDb7の場合 □→Ab7→◇→Db7 □→D7→◇→Db7 ◇にその直前と同じコードが入るものは除外するので、以下の6つだけが候補となる □→Ab7→Abm7→Db7 □→Ab7→D7→Db7 □→Ab7→Dm7→Db7 □→D7→Abm7→Db7 □→D7→Ab7→Db7 □→D7→Dm7→Db7 この□の部分(1小節目のコード)に、続くコードに対してII-VとSec.Dの各2通りが入る(p5下行と半音下行) ので、以下の24通りが全てOKとなる 「A7→D7→Dm7→Db7」 「Am7→D7→Dm7→Db7」 「Eb7→D7→Dm7→Db7」 「Ebm→D7→Dm7→Db7」 「A7→D7→Ab7→Db7」 「Am7→D7→Ab7→Db7」 「Eb7→D7→Ab7→Db7」 「Ebm7→D7→Ab7→Db7」 「A7→D7→Abm7→Db7」 「Am7→D7→Abm7→Db7」 「Eb7→D7→Abm7→Db7」 「Ebm7→D7→Abm7→Db7」 「A7→Ab7→Dm7→Db7」 「Am7→Ab7→Dm7→Db7」 「Eb7→Ab7→Dm7→Db7」 「Ebm7→Ab7→Dm7→Db7」 「A7→Ab7→D7→Db7」 「Am7→Ab7→D7→Db7」 「Eb7→Ab7→D7→Db7」 「Ebm7→Ab7→D7→Db7」 「A7→Ab7→Abm7→Db7」 「Am7→Ab7→Abm7→Db7」 「Eb7→Ab7→Abm7→Db7」 「Ebm7→Ab7→Abm7→Db7」 ●前半2小節の後のコードからSec.Dで後半2小節の前のコードに進む場合 後半2小節の前のコードがDm7の場合 □→◇→Dm7→G7 □→◇→Dm7→Db7 ◇はドミナントコードに限定しているので、p5下行と半音下行で以下の4つだけが候補となる □→A7→Dm7→G7 □→Eb7→Dm7→G7 □→A7→Dm7→Db7 □→Eb7→Dm7→Db7 この□の部分(1小節目のコード)に、続くコードに対してII-VとSec.Dの各2通りが入る(p5下行と半音下行) ので、以下の16通りが全てOKとなる 「E7→A7→Dm7→G7」 「Em7→A7→Dm7→G7」 「Bb7→A7→Dm7→G7」 「Bbm7→A7→Dm7→G7」 「E7→Eb7→Dm7→G7」 「Em7→Eb7→Dm7→G7」 「Bb7→Eb7→Dm7→G7」 「Bbm7→Eb7→Dm7→G7」 「E7→A7→Dm7→Db7」 「Em7→A7→Dm7→Db7」 「Bb7→A7→Dm7→Db7」 「Bbm7→A7→Dm7→Db7」 「E7→Eb7→Dm7→Db7」 「Em7→Eb7→Dm7→Db7」 「Bb7→Eb7→Dm7→Db7」 「Bbm7→Eb7→Dm7→Db7」 後半2小節の前のコードがD7の場合 □→◇→D7→G7 □→◇→D7→Db7 ◇はドミナントコードに限定しているので、p5下行と半音下行で以下の4つだけが候補となる □→A7→D7→G7 □→Eb7→D7→G7 □→A7→D7→Db7 □→Eb7→D7→Db7 この□の部分(1小節目のコード)に、続くコードに対してII-VとSec.Dの各2通りが入る(p5下行と半音下行) ので、以下の16通りが全てOKとなる 「E7→A7→D7→G7」 「Em7→A7→D7→G7」 「Bb7→A7→D7→G7」 「Bbm7→A7→D7→G7」 「E7→Eb7→D7→G7」 「Em7→Eb7→D7→G7」 「Bb7→Eb7→D7→G7」 「Bbm7→Eb7→D7→G7」 「E7→A7→D7→Db7」 「Em7→A7→D7→Db7」 「Bb7→A7→D7→Db7」 「Bbm7→A7→D7→Db7」 「E7→Eb7→D7→Db7」 「Em7→Eb7→D7→Db7」 「Bb7→Eb7→D7→Db7」 「Bbm7→Eb7→D7→Db7」 後半2小節の前のコードがAb7の場合 □→◇→Ab7→G7 □→◇→Ab7→Db7 ◇はドミナントコードに限定しているので、p5下行と半音下行で以下の4つだけが候補となる □→Eb7→Ab7→G7 □→A7→Ab7→G7 □→Eb7→Ab7→Db7 □→A7→Ab7→Db7 この□の部分(1小節目のコード)に、続くコードに対してII-VとSec.Dの各2通りが入る(p5下行と半音下行) ので、以下の16通りが全てOKとなる 「E7→A7→Ab7→G7」 「Em7→A7→Ab7→G7」 「Bb7→A7→Ab7→G7」 「Bbm7→A7→Ab7→G7」 「E7→Eb7→Ab7→G7」 「Em7→Eb7→Ab7→G7」 「Bb7→Eb7→Ab7→G7」 「Bbm7→Eb7→Ab7→G7」 「E7→A7→Ab7→Db7」 「Em7→A7→Ab7→Db7」 「Bb7→A7→Ab7→Db7」 「Bbm7→A7→Ab7→Db7」 「E7→Eb7→Ab7→Db7」 「Em7→Eb7→Ab7→Db7」 「Bb7→Eb7→Ab7→Db7」 「Bbm7→Eb7→Ab7→Db7」 後半2小節の前のコードがAbm7の場合 □→◇→Abm7→G7 □→◇→Abm7→Db7 ◇はドミナントコードに限定しているので、p5下行と半音下行で以下の4つだけが候補となる □→Eb7→Abm7→G7 □→A7→Abm7→G7 □→Eb7→Abm7→Db7 □→A7→Abm7→Db7 この□の部分(1小節目のコード)に、続くコードに対してII-VとSec.Dの各2通りが入る(p5下行と半音下行) ので、以下の16通りが全てOKとなる 「E7→A7→Abm7→G7」 「Em7→A7→Abm7→G7」 「Bb7→A7→Abm7→G7」 「Bbm7→A7→Abm7→G7」 「E7→Eb7→Abm7→G7」 「Em7→Eb7→Abm7→G7」 「Bb7→Eb7→Abm7→G7」 「Bbm7→Eb7→Abm7→G7」 「E7→A7→Abm7→Db7」 「Em7→A7→Abm7→Db7」 「Bb7→A7→Abm7→Db7」 「Bbm7→A7→Abm7→Db7」 「E7→Eb7→Abm7→Db7」 「Em7→Eb7→Abm7→Db7」 「Bb7→Eb7→Abm7→Db7」 「Bbm7→Eb7→Abm7→Db7」 ◆FMC3のルールを拡張する (Key=C) - 32通り FMC3のルールのうち、「2小節パターンの、後ろのコードは必ずドミナント7thコードとする」 という条件は音楽的には必須なものではない。後半2小節の後ろは全体4小節の最後なので ドミナント7thコードが必須であるが、前半2小節の後ろのコードはマイナー7thコードであっても OKであり、この場合、前半2小節の前のコードは、マイナー7thコードの連続は除外しているので、 ドミナント7thコードに限定される。 つまり、前半2小節を「ドミナント7thコード→マイナー7thコード」と逆順にしたパターンを加える。 このような前半2小節から繋がる後半2小節については、その先頭(3小節目)のコードに制限が出る。 後半2小節の前(3小節目)がマイナー7thコードでは、2小節目→3小節目がマイナー7thコードの 連続となり、コード進行の理由付けが出来ないので不適である。 従って、ここで考える後半2小節は「ドミナント7thコード→ドミナント7thコード」というSec.Dになり、 全体の3小節目はドミナント7thコードだけとなり、2小節目→3小節目はツーファイブとして進行する。 そして、前半2小節の前、つまり全体の1小節目のパターンには、以下の2つがある。 ・1小節目のコードからSec.Dで2小節目のm7thコードに進む ・1小節目のコードからExt.Dで後半2小節の前のコードに進む このrootは「完全5度下行か半音下行(裏5度進行)のいずれか」の2通りで進行する 全体の3小節目はドミナント7thコードだけなので、G7に進むのは、D7(p5下行)と、Ab7(半音下行)。 Db7に進むのは、Ab7(p5下行)と、D7(半音下行)。つまり、組み合わせは以下の4通り。 D7→G7 Ab7→G7 Ab7→Db7 D7→Db7 ここで前半2小節の前、1小節目のコードの連結パターンは以下のいずれか。 ・1小節目のコードからSec.Dで2小節目のマイナー7thコードに進む ・1小節目のコードからExt.Dで3小節目のドミナント7thコードに進む ●1小節目のコードからSec.Dで2小節目のマイナー7thコードに進む場合 後半2小節の前のコードがD7の場合 □→◇→D7→G7 □→◇→D7→Db7 ◇はm7thコードに限定しているので、p5下行と半音下行で以下の4つだけが候補となる □→Ebm7→D7→G7 □→Am7→D7→G7 □→Ebm7→D7→Db7 □→Am7→D7→Db7 この□の部分(1小節目のコード)に、続くコードに対してSec.Dの2通りが入る(p5下行と半音下行) ので、以下の8通りが全てOKとなる 「Bb7→Ebm7→D7→G7」 「E7→Ebm7→D7→G7」 「Bb7→Am7→D7→G7」 「E7→Am7→D7→G7」 「Bb7→Ebm7→D7→Db7」 「E7→Ebm7→D7→Db7」 「Bb7→Am7→D7→Db7」 「E7→Am7→D7→Db7」 後半2小節の前のコードがAb7の場合 □→◇→Ab7→G7 □→◇→Ab7→Db7 ◇はm7thコードに限定しているので、p5下行と半音下行で以下の4つだけが候補となる □→Ebm7→Ab7→G7 □→Am7→Ab7→G7 □→Ebm7→Ab7→Db7 □→Am7→Ab7→Db7 この□の部分(1小節目のコード)に、続くコードに対してSec.Dの2通りが入る(p5下行と半音下行) ので、以下の8通りが全てOKとなる 「Bb7→Ebm7→Ab7→G7」 「E7→Ebm7→Ab7→G7」 「Bb7→Am7→Ab7→G7」 「E7→Am7→Ab7→G7」 「Bb7→Ebm7→Ab7→Db7」 「E7→Ebm7→Ab7→Db7」 「Bb7→Am7→Ab7→Db7」 「E7→Am7→Ab7→Db7」 ●1小節目のコードからExt.Dで3小節目のドミナント7thコードに進む場合 後半2小節の前のコードがD7の場合 □→◇→D7→G7 □→◇→D7→Db7 ◇はm7thコードに限定しているので、p5下行と半音下行で以下の4つだけが候補となる □→Ebm7→D7→G7 □→Am7→D7→G7 □→Ebm7→D7→Db7 □→Am7→D7→Db7 この□の部分(1小節目のコード)に、1つとばした3小節目に対してExt.Dの2通りが入る (p5下行と半音下行)ので、以下の8通りが全てOKとなる 「A7→Ebm7→D7→G7」 「Eb7→Ebm7→D7→G7」 「A7→Am7→D7→G7」 「Eb7→Am7→D7→G7」 「A7→Ebm7→D7→Db7」 「Eb7→Ebm7→D7→Db7」 「A7→Am7→D7→Db7」 「Eb7→Am7→D7→Db7」 後半2小節の前のコードがAb7の場合 □→◇→Ab7→G7 □→◇→Ab7→Db7 ◇はm7thコードに限定しているので、p5下行と半音下行で以下の4つだけが候補となる □→Ebm7→Ab7→G7 □→Am7→Ab7→G7 □→Ebm7→Ab7→Db7 □→Am7→Ab7→Db7 この□の部分(1小節目のコード)に、1つとばした3小節目に対してExt.Dの2通りが入る (p5下行と半音下行)ので、以下の8通りが全てOKとなる 「Eb7→Ebm7→Ab7→G7」 「A7→Ebm7→Ab7→G7」 「Eb7→Am7→Ab7→G7」 「A7→Am7→Ab7→G7」 「Eb7→Ebm7→Ab7→Db7」 「A7→Ebm7→Ab7→Db7」 「Eb7→Am7→Ab7→Db7」 「A7→Am7→Ab7→Db7」講座(36) ちょっとだけ追加 - 「メロディーの作り方」
- 本項は2016年の特講にて、上までの講座(35)に追加した、今年のオリジナルである(^_^)
- コードについては解説終了。簡単には、既存の自分の好きな曲のコードを取って(「耳コピ」。これは難しいので長嶋に依頼すべし)、それを同等の機能のコードに置き換えたり、ドミナントモーションの理論に対応してコードを加えたり、リズム/ビートを変えたりすればOK。コード進行に著作権は無いので、完全に同一のコード進行の楽曲でも、メロディーを変えればオリジナルと主張できる(^_^;)
- メロディーの1つ1つの音の高さを、オクターブ内の12音からどう選ぶか、というお話が今回のメイン
- メロディーの1つ1つの音のタイミング(リズム)は、皆んなのセンスに任せる(^_^;)
- メロディーの音は、その時に鳴っているコードの構成音であれば確実に全てOK。コードがFM7ならFかAかCかE。その瞬間のコードだけに注意すればいいので、キーとか転調とかは気にしない
- その時に鳴っているコードの構成音のうち、rootの音(FM7ならF音)はベースとかぶる事がとても多いので、次々にコードのrootをたどったメロディーはとてもダサいものになる(^_^;)。ただし、ずっとrootを外し続けるとまた不安になる・・・
- その時に鳴っているコードの構成音のうち、5thの音(FM7ならC音)は、ベースやバッキングの楽器(ギターとかピアノ)とかぶる事が多いので、適切に使うことが大切
- その時に鳴っているコードの構成音のうち、3度と7度の音(FM7ならA音とE音)は、そのコードのキャラを決定付ける音なので、うまく活用すると、いいカンジのメロディーとなりやすい。ただしボーカルの場合には、跳躍で歌いにくい(難しい)というリスクもある
- その時に鳴っているコードの構成音(1/3/5/7)以外の音、として次に候補となるのは、そのキーにおけるダイアトニックスケールである。つまりドレミファソラシのうち、コードに使われていない残り3音である。キーがCでコードがFM7である場合には、このコードはIV(サブドミナント)であり、メロディーとして使う候補は、コード音のF・A・C・Eを除いた、G・B・Dである。実はこの3音は、キーに設定した楽譜において、1/3/5/7の4和音の上に、さらに団子3兄弟のように9/11/13と串刺しに並べた3和音である。この、「ダイアトニックスケールの構成音だけを用いて、あるダイアトニックコード(4和音)の上に積んだ3和音」のことを、Upper Structured Triad (UST - 上部構成3和音)という。キーがCの場合、IのCM7のUSTはDm、IIのDm7のUSTはEm、IIIのEm7のUSTはF、IVのFM7のUSTはG、VのG7のUSTはAm、VIのAm7のUSTはBdim、VIIのBm7-5のUSTはC、となる。基本的にはこれらUSTの3音はテンションノートと言って、メロディーに使った場合に、その部分のコードと緊張感のある「良い不協和音」として使えるものが大部分だが、一部に、「使ってはイケナイ不協和音」というavoid noteがあるので注意が必要である。このあたりを書いたのが、配布資料の12ページである
- ここまでの話は、全て登場する音はダイアトニックスケール内に限り、登場する和音もダイアトニックコードであった。しかし、II-V、Sec.D、Sub.D、Ext.Dなど、キーのダイアトニックスケールに無い構成音を持つコード(ノンダイアトニックコード : NDC)がどんどん出て来るところがアレンジの醍醐味である。このNDCに対して、メロディーでどの音が使えるか、というのはなかなか悩ましい(^_^;)
- NDCの場合には、そのNDC自体で強いキャラを持っている(たいていの場合にはドミナント7thコードでトライトーンの解決を希求する)ので、そのNDCのrootや5th、あるいは3rdや7thだけで、十分にインパクトのあるメロディーを構成できる
- もちろんNDCの場合にも、そのキーのダイアトニックスケールの音を使ってUSTを乗せる、という戦略もOKである。実際にはさらに込み入った評価が必要となるが、このあたりを書いたのが、配布資料の13ページである
- 以上で、刻々と変化するコードに乗せるメロディーの音の高さを選ぶ、という部分の理論的な基礎は確立している。あとは耳を頼りに、実際に作ってみよう(^_^)
講座(37) さらに追加 - 「適当に選んだ単一ピッチのメロディーにコード進行を当てる」
- 本項は2017年の特講にて、上までの講座(36)に追加した、今年のオリジナルである(^_^)
- ここまで「コードありき」で進めてきたが、逆もまた真なり。適当な音をメロディーだと見做して、そこにコードを付けるという作曲/アレンジもまた可能である
- 「適当な音」が上下に変化・跳躍すると、メロディーとなるが、そこにはスケールなりコード感が必要になる。そこでここでは、「適当な単一ピッチの音」、つまり、リズムを適当に刻んでモールス符号のようになって続くメロディー、という極端なサンブルで考察する。単一でもこれだけ出来るので、適当なところでまた別の音に移動して同じようなことをすればいいので、もはや可能性は無限である
- ここでは本講座の「4小節ループ」音楽でなく、1小節目をトニックのC/Amとして始める4小節パターンの例として提示する。従ってこの4小節にから続くのは、ループに戻る限るものではない。ただし少なくともトニックに戻ることは原理的に常に可能なので、面白みに欠けるとしても4小節ループとしても使用できる
- ここではとりあえずのキーをC major / A minor、すなわち調号として#もbも何もない、とする。移動ドで階名を言うとすれば、Tonal Centerの「C」が「ド」である
- ここではコードを基本的にはTriad、すなわち3和音とする。これはメロディー音がコードの構成音に無いテンションである場合が多いからであり、ここのTriadに「rootから短7度の7th」または「rootから長7度のmajor 7th」を加えるかどうか、は慎重に耳を頼りに確認すること。ヘタに加えると濁ることも少なくない
- ここではスラッシュ「/」は「小節を分割」でなく「分数コード」の意味であるので注意
- メロディーが単一の「ド」(C)だけだとしたら・・・
- パターン例 : C → Bb → F → Ab
- パターン例 : C → D → F → Ab
- パターン例 : C → Eb → F → Ab
- パターン例 : C → Dm → Eb → Db
- パターン例 : C → Ab → Bb → F
- パターン例 : C → Bb → Eb → F#
- パターン例 : Am/A → Caug/G# → C/G → Am6/F#
- パターン例 : Am/A → C/G → Am6/F# → Fmaj7/F
- メロディーが単一の「ミ」(E)だけだとしたら・・・
- パターン例 : C → A → D → G
- パターン例 : C → E7 → Am → Em7
- パターン例 : Am → Bm → G → E7
- メロディーが単一の「ソ」(G)だけだとしたら・・・
- パターン例 : C → Bb → F → Ab
- パターン例 : C → Eb → Bb→F
- パターン例 : C → Am → Bb → G7
- メロディーが単一の「シ」(B)だけだとしたら・・・
- パターン例 : CM7 → B7 → Em7 → A7
- パターン例 : C → E7 → Am9 → F#dim
- メロディーが単一の「ラ」(A)だけだとしたら・・・
- パターン例 : C → A → D → F
- パターン例 : C → D → F → A
- パターン例 : Am → G → F → G
- メロディーが単一の「レ」(D)だけだとしたら・・・
- パターン例 : C → G → F → D
- パターン例 : C → D → F → G
- パターン例 : C → Bb → F → G
- メロディーが単一の「シb」(Bb)だけだとしたら・・・
- パターン例 : C → Eb → Bb → Eb
- パターン例 : C → Bb → Fsus4 → Eb
- メロディーが単一の C#, Eb, F, F#, Ab、という残りの5パターンについては、スタートのCに対してavoid(禁則)のぶつかり方をしているので除外する。ただしスタートのコードをCでないように避ければ、この4音もまたメロディー音の候補として除外されるものではない